ある晴れた午後に近所の大病院に来ました。
白くて四角いその建物に吸い込まれるように、たくさんの人が病院の入り口に入っていくのを眺めていると、真っ白な白衣のお医者さんや車椅子で移動しているおじいさん、一見元気そうに見える男の子などの姿が見えます。
私は、その人々の間をすり抜けて病院に入り、「自分は目指すのは何階だろう?」と思って案内を探します。
病院に入ると独特の消毒液のにおいと、低い声で控えめにざわざわと聞こえる声が入り混じって、「ああ、病院に来たんだなあ」となんだか懐かしく思います。
なぜなら、前回こんなに大きな病院に来たのは子供の頃で、母親に手を引かれて注射を打ちに来たのですが、あの時は違う病院だったのに、今いるこの病院と同じような消毒液のにおいと待合室や廊下を歩く人々の低くて抑え気味のざわざわという声を聞いていたので、自分にはなんだか不思議な感覚がするのです。
そう、子供の頃は子供の頃で、病院の独特なにおいや雰囲気が珍しかったし、今の自分にとってもやはり非日常のように感じられる「病院」という場所は、大人になってからも何もかもが新鮮に感じられたのです。
僕は、病院という場所が好きだったわけではないけれど、学校を休んで母親に手を引かれて来る病院は、たくさんの大人たちがいて、行き交う言葉がはっきりとせず大きな低い波となって聞こえてくるその空間が、まるで子守歌のように感じてうっとりと眠くなってきます。
僕の母親は、決して優しい人ではなかったので、僕を励ますことや僕を気遣うことはなかったけれど、繋いだ手のぬくもりから、もしかしたら自分は母に大切にされてるかもしれない、とそんなことを思っていました。
病院の帰りにはいつも病院のそばにあるドーナツ屋さんで母と2人ご飯を食べて帰るのだけれど、僕は緊張して何が食べたいか分からず、母の目をまっすぐに見ることもできずに、俯いたまま出されたものをもそもそと食べていました。
すると、母も私に何も言わずに食事をして、ただお皿とカトラリーがカチャカチャとぶつかる音と、店内の陽気なBGMを一所懸命に聞きながら、この場をやり過ごすのです。
もしかしたら母は、僕が注射を泣かずに頑張ったから、ご褒美としてドーナツを食べさせてくれているのかな?とも思うけれど、帽子の影に隠れた母の目は、どこか不機嫌そうにも感じられるし、そうではないかもしれない。
僕は、注射が好きでも嫌いでもなかったけれど、大抵の子供が嫌がる注射を何ともない顔でやってのけることがちょっと自慢だったので、いつも「平気!」だと元気よく答えていました。
誰かに「偉いね」と言われた覚えもないけれど、僕はいつだって強くありたいと思っていたし、そうあることで誰かが喜ぶと思っていたのかもしれないし、だけどこうやって母に何かをしてもらった時の僕はいつも弱くて泣きそうになってしまうから、素直に母に甘えることもできなくて、子供らしく可愛く母にお礼を言うこともできなかったのです。
そう、母は僕から見たらいつも無表情で不愛想なんだけれど、母が僕のために作ってくれるお弁当には、確かにあたたかいものを感じていました。
それは、お弁当箱のふたを開けるといつも、そこには僕の好物ばかり入っていたからかもしれないし、お昼休みに手に取るお弁当箱がまだほんのりとあたたかさを残していたからかもしれません。
友達の前で食べる母のお弁当は「うれしい!おいしそう!」とは口が裂けても言えずにいつもクールに口へ運んでいるけれど、友達のたわいもない話を聞きながら食べるおいしいお弁当は、私の心の中の何かをいつも動かすのです。
もしかしたらそれは、お弁当を食べることであの感情が私の中に湧いてくるのかもしれないし、本当は何も感じていないのかもしれない。
けれど、他の子のお弁当と比べて「自分のお弁当はとても立派だ!」というのが私の誇りだったし、私は母の作るお弁当が大好きだったので、大人になってからも自分で自分にお弁当を作って会社に持って行っていったのだけれど、なぜか母の作ったお弁当箱を開けた時のようなあのワクワク感を感じられないのです。
それは、自分で作っているから、すでに弁当箱の中身を知っているからかもしれないけれど、そうではなくて、もっと何かが足りないと、昼休みのオフィスの控えめな喧噪を肌に感じながら、オフィスのざわざわ感で考えるのがどうでも良くなるような感覚を持ちながら、何かの違和感を感じるのです。
そして、私はいつしかお弁当を作らなくなって、友達とお昼を食べに行ったり、会社に行く途中で美味しそうな弁当屋さんに寄ってテイクアウトをしたりするようになって、母のお弁当のことを忘れて行ったのですが、そこに寂しさだったり、なつかしさだったりがなくなっていることに気がついて、「あ、これが成長なのかもしれない」とそんなことを思うのです。
母が、どんな気持ちで私のお弁当を作っていたのかは今もまだ知らないけれど、私の中の記憶でいつも美味しかった母のあのお弁当は、真似をしても私には作れないし、どのレシピ本を見ても同じ味を再現できません。
だから、私はいつしか母を追い求めることをやめて、目の前の友だちと会話することにして、楽しく食事を味わうことにしたのです。
そうすると、友達は私の話をしっかり聞いてくれて、私もそれに笑顔でこたえることができて、だから、母のあのお弁当が再現できなかったとしても、こんなところにも幸せがあったんだと、私は今の私のささやかな幸せをきちんと噛み締めることが出来たような気がしています。
記憶の中の母は、笑っていたのかそうでなかったのか分からないけれど、今思い出した母の口元はたしかに少し、笑顔だったのかもしれません。
母はいつも私に何も語り掛けなかったので、私も母に何も聞かなかったけれど、目の前の友達は私が質問をしたら何でも優しくこたえてくれて、それを聞いた私はまた友達に何かを伝えることが出来るのです。
だから、私はあの日の母の笑顔を思い出せなくてもきっと、目の前の友達が笑ってくれていたら、私も幸せなんだと思えるのかもしれません。
ひとつ、爽やかな風が頭に流れていきます。
ふたつ、身体がだんだん軽くなっていきます。
みっつ、大きく深呼吸をして、頭がすっきりと目覚めます。






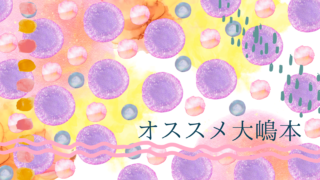




コメント