私の人生を一番大きく変えてくれた一冊と言えば、間違いなく【それ、あなたのトラウマちゃんのせいかも?】です。
この本を読んではじめて「自分の今までのどうしようもないことは、すべてトラウマで解離している症状だったんだ!」と腑に落ちました。
そして、意識では「母親が大嫌いだ」と思っていたはずなのに、私の人生はずっと母親を庇い続けていたことに気づいたんです。
初回に読んだ時は「そうなの!人間のこんな話が聞きたかったの!」と感動して、でも「〇〇の恐怖」×7回の〇〇を探る方法がよく分からなかった。
2回目に読んだ時は、仕事の激務から帰宅した後の深夜にコツコツ読んでいました。
この頃は文字が読めなくなっていたので、1日1ページとか2ページを丁寧にマーカーを引きながらかなり遅いペースで読み進めていたのですが、あるページを読んだ時にこれまでのことが自分の中ですべて糸で繋がった衝撃が走りました。
母親が苦痛で「ギャー!ギャー!」と叫ぶたびに、子どもの猿は一生懸命に母親の苦痛を止めるスイッチを探して止めようとあたふたする。(p375)
私は心理学科卒なので、このお猿さんの実験は知っていました。
だけど、それが自分のこととは別世界の話だと思っていたんです。
この箇所を読んでいた夜、すでに午前2時とか3時で翌日も仕事だったのですが、夜中中1人で大号泣しました。
そうか、私は母親が苦しまないように一生懸命苦痛を止めるスイッチを探していたんだ、と。
この時、34歳でした。
今回はそんな私の人生を変える大きな転機になったトラウマちゃんの本を再読して、改めて気づいたことを記しておこうかと思います。
ちょっとでも苦しいなら休め!
トラウマの人は、ストレス刺激を受けた時に「普通の人」とは真逆のストレス反応をします。
普通の人は、ストレスを受けた瞬間「戦うor逃げる」に瞬時に対応できるよう、ぎゅーん!と緊張度が上がります。
そして、目の前から危機が去ってある程度時間が経過したら、緊張は落ち着いて元の状態に戻ります。
しかし、トラウマの人は普段から緊張度が高くて、ストレスを受けた瞬間に緊張が下がります。
なぜなら、トラウマの人は安静時に「死の恐怖」をダイレクトに感じてしまうのが怖くて、常に嫌な過去や腹立つ人のことを思い出して緊張を高めているからです。
トラウマの人の緊張は、「死に直面した時の恐怖」に匹敵します。
トラウマの人は高い緊張を鎮めるために、ストレス刺激をコンスタントに仕入れています。
普通の人とは逆の反応なので、普通の人がストレス時に緊張が上がるのに対して、トラウマの人はストレスで緊張が下がるから、だからストレス刺激があった方がトラウマの人はストレスホルモンの値が低くなる。
(ここらへんの話はトラウマちゃんの本にめちゃくちゃ詳しく書いているので、未読の方はぜひ読んでください!)
トラウマを受けた人が自身の悲惨な体験を「こんなの大したことないっすよ」って感じで淡々と話されるのは、悲惨な経験であればあるほどトラウマの“回避”と“麻痺”が起こっているから。
すると、トラウマの人は他人から見ると淡々としているように見える。
そんな私も「私のトラウマなんか~!(笑)」っていうようなタイプだったので、完全にアウトなやつでした。
病気で苦しんでいるはずなのに、苦しんでいる時にこそ緊張のホルモンが下がってしまうので「自分は仮病を使っているのかも?」と思ってしまう。(p49-50)
これ、すごくよく分かります。
「しんどい…今日休みたい…」と思いながら、いやいや病は気からって言うしと自分に言い聞かせて出勤していたけど、他人から見たら「休めよ!もっと早く言え!」っていう体調だったことが何度もある。
「この仕事合わない…辛い…辞めたい」となんとなく自分の中の赤信号を感じているんだけど、「でもこれって甘えかも」と思って働き続けて大変なことになる。
辛い時に「辛い!」っていう顔ができませんでした。
辛い時でも普通に振る舞えてしまうから、めちゃくちゃしんどい時にも「いつも元気だね!」と声掛けされたりするので、自分でも「まだ頑張れるでしょ」と思ってしまう。
そうなってしまった原因の1つだと思っているのが、母親の対応です。
私が「しんどい」と言った時に、母親は「もうちょっと頑張れるでしょ」と必ず言う。
それは私が「もうお腹いっぱい」と言った時に、母親が「これだけ食べて」と言うのに似ている。
自分としては「ほんっとうにこれ以上無理!!」という限界値で宣言しているのに、母親はなぜか「まだいけるでしょ」という考えであること。
この認識がもう本当に嫌で嫌で。
母親に「まだ大丈夫でしょ」といった対応をされるのが心底嫌なことが分かったのはトラウマ治療が進んできてからだったのですが、そのたびに「だから、もう無理だって言ってんの!」とぶち切れてました。
小さい頃から「まだ大丈夫でしょ」と母親にいつも言われるから、大人になって自分でいろいろ決めなければいけない時も「しんどいと思っているけどまだ大丈夫かも」と自分の限界を見て見ぬふりをしてしまっていた。
今振り返ると、私が「しんどい」を出せずに淡々としてしまっていたのは、小学1年生の時からでした。
FAP療法が進んできてから知ったことなのですが、私には未だに思い出せないトラウマが1つあります。
小学校1年生の時の担任の先生に吊るし上げられていたことです。
私の中では、この先生はとても優しくて良い先生だったので、学年が上がってもまた「会いたい」と思っていたぐらいでした。
けれど、何かのきっかけで母親とトラウマの話になった時に、20数年越しに知った真実は「え?あの先生かなりひどかったで!」ということ。
良く言えば私はゆっくりのマイペースタイプだったので、それで担任の先生に目をつけられてクラスを巻き込んで孤立させられていたそうです。
母親はものすごく怒っていた。当時も怒ってくれていたのかは不明ですが…。
どうりで、私は小学校1年生から変だったわけだ。
気管支炎の入院、抜毛症はその後高校1年生まで続き、希死念慮、強烈な恥の感覚が始まったのもこの頃です。
気管支炎になった朝のことはよく覚えています。
息ができなくてかなり苦しかったのですが、「息ができない…」と母親に伝えてもいまいち深刻さが伝わりませんでした。
とりあえず近所の医者に行くということで放置されていて、その間に私は手持無沙汰でおもちゃで遊んでいたので(相当苦しかったんだけれど)、それも母親には「普通」に見えていて、まったく私の身体的な辛さが伝わっておらず逆に「余計なことして!」と怒られました。
さらにその後数年間、母親に「息ができない…」と言った時の私の物真似をされて爆笑されていました。
死ぬほどしんどかったんだけどなあ!
ととても心外なのですが、すでにあの頃から私はトラウマで、辛い時ほど緊張ホルモンが下がってしまって“冷静”に見られていたのかもしれません。
教室に蜂が入ってきても微動だにせずみんなから「すげー!」と言われるような“冷静”さだったので、その後トラウマ治療をしていく中で「その場ですぐ怒る」「ちゃんと驚く」の訓練を自主的にしていたのですが、すぐ反応することに慣れるにはなかなか苦労しました。
なので、トラウマ持ちのみなさん!
自分がちょっとでも「しんどいかも?」と思ったら、それは普通の人にとったらかなりしんどい状態なので、迷わず休んでください。
私はヘルニアになってから、身に染みて感じています。
それまで人生で何度も「なんで起き上がれないんだろう?」と思うことがありました。
自分の感覚では「もう十分休んだ」とか「そんなに疲れてないでしょ」と思っているんです。
だけど、ヘルニアになってから自覚したのですが、ちょっとでも「あーなんか怠いかも」と感じて起き上がれない時って、無理して起き上がっても頭が回らなかったり体が重かったりします。
それで結局、無理して起き上がったのに何も満足にできなかったとなるので、頭では「そんなに疲れてないでしょ」と思っていても、体が動きたがらないようだったら「疲れてるんだな」と認めて休むことにしています。
(ここらへんはポリヴェーガル理論の説明が分かりやすいかもです→【「ポリヴェーガル理論」がやさしくわかる本】レビュー)
「こんなことが起きたらどうしよう…」は心的外傷関連の回避
上にも書いてましただ、すでに私は小学校1年生の時になんらかの大きなトラウマを持っていて、担任の先生のイメージが書き換えられてしまっていました。
このトラウマはFAP療法でカウンセラーさんに取ってもらったのですが、未だに私はこの先生の怖さやその時の恐怖を思い出すことができません。
ただ、入院後に担任の先生と2人っきりで放課後の教室に残って、私だけ合格していない国語の朗読をやらされている時の緊張は、喉から太い手が出てきて窒息するような息苦しさがあったことは覚えています。
そして、その時に先生に吐いた些細な嘘がバレるのを恐れて、7年間ほど毎晩強迫的な儀式をしないと眠れなくなりました。
そしてちょうどこの頃、夏休みに観た戦争映画が怖かったのか、家の上を飛行機が飛ぶたびに「爆弾が落ちてきませんように、爆弾が落ちてきませんように」と必死で願っていました。
先生に吐いた嘘がバレませんように、と必死で祈るのと同じぐらい「爆弾が落ちてきませんように!」と心の底から一生懸命祈り続けました。
本当に怖かったんです。
過去の嫌なことを繰り返し思い出して怒っていたり、または、考えてもどうしようもない将来ことを不安に感じて「こんなことが起きたらどうしよう?」、「あんなことが起きたらどうしよう?」とその不安に対する対応を調べるのが止まらなくなったりする。(p52 原文まま)
小学校の時から、とにかく「あんなことが起きたらどうしよう?」ばっかりで、まったく心が休まりませんでした。
遠足の前日には「本当に明日遠足なの?」と日付を間違っていないか何度も確認する。
でも、不安なことを家族にも誰にも言えない。
家族で電車に乗って遠出した時、家族はみんな寝ているのに私だけ起きているのですが「もうそろそろじゃないの?」と降りる駅が分からないので不安で何度も家族を起こす。
「嘘がバレたらどうしよう?」「怒られたらどうしよう?」「明日起きれなかったらどうしよう?」
…………………………。
たくさんの「どうしよう」は、大人になってからも相変わらず続いていました。
「今日、本当に休みなの?」と何度もシフトを確認する。
「さっきはああ言ったけど実は違うかも?」と家に帰ってから不安になってきて、夜も眠れずずっと後悔してしまう。
毎日毎日「明日こそ嫌なことが起きるかも」と思って過ごしていたので、明日になるのが怖くて朝日が昇ってからしか安心して眠れない。
普通の人から見たらただの心配性なので、「また言ってる!」とよく笑われていました。
「そんなこと起きませんって!」と。
でも、自分の中の恐怖は尋常じゃないので、新しい人に会うたび、新しい場所に行くたびに心臓が飛び出るほど緊張していて吐きそうでした。
今でも稀にちらっと嫌なことを思い出していたり、腹立つ人のことを考えて目の前のことに集中できていなかったりするのですが、この嫌なことを考え続けてしまうことが実はトラウマの回避行動なんですよね。
「あ!今、嫌なことを考えてフリーズしてた!」と気づくと、それがトラウマが原因であるかもしれないと思ってみる。
将来のお金の不安で眠れない夜や、明日の不安な予定のことをぐるぐる考えてしまう時も、「あ!ここにトラウマがあるのかも?」と思ってみる。
考えるのが止まらないのは、“死の恐怖”を回避したいから。
トラウマちゃんの本には「〇〇の恐怖」×7回を唱えて恐怖に浸ることで、解離して恐怖が増幅してしまうことを食い止める方法がとても詳しく書かれています。
素晴らしい本です。
「〇〇の恐怖」×7回を唱えなくても、その仕組みを知るだけかなり大きなものが癒されるのではないかと思います。
目の前のことに集中できない自分がダメなんじゃない。
いつまでも根に持って怒っている自分が醜いんじゃない。
まだ起こってもいない将来の心配をするのがムダとかそういうことじゃない。
不快な感情が自分の中で渦巻いて「今ここ」からトリップしているのなら、そこに自分のトラウマが隠れているのかもしれません。
ーーー
来月の【心の栄養読書会】の課題本は、トラウマちゃんの本です。
良ければぜひ語り合いましょう!

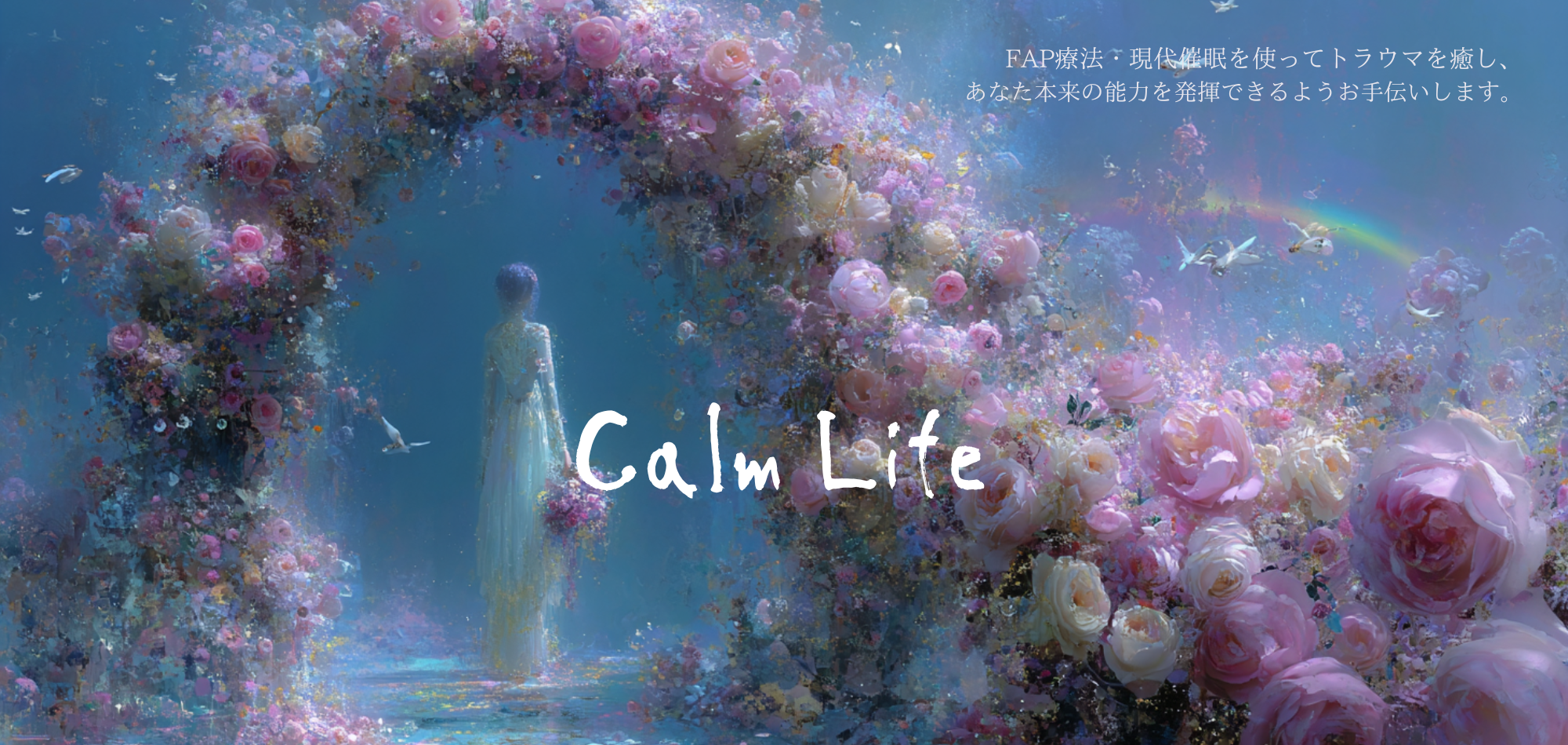
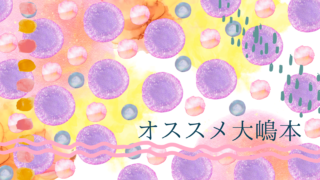










コメント