しばらく経ってもリエが口を開くことはなかった。
私はなんだか少しガッカリした気持ちになったけれど、リエと黙ったまま静かな教室で、窓の外の向こうから聞こえるかすかな自動車の音を聞きながら過ごす時間は、なんだか心地良い感じがしていました。
私がリエをチラッと眺めると、リエは体全体を硬直させたまま真っ直ぐ立っているようで、その顔は俯き加減で「あ、私に気遣って私の顔を見れないんだな!」というのが分かります。
私はそんなリエの様子を見て、椅子から立ち上がり、窓の外の大きな夕陽が山の向こうに沈んでいく様子を見て「帰ろうか」とリエに声を掛けました。
リエは震えながら小さく頷いたようで、私はそれを確認すると机の横に掛けていた鞄を取って、カツカツカツと床を踏みながら教室のドアの方へ歩いて行きます。
廊下に出ると野球部の声が聞こえてきたり、吹奏楽部の練習している音が聞こえてきましたが、私はリエが後ろからちゃんとついてきているかを足音をこっそり聞きながら確認します。
無言のまま2人で長い長い廊下を歩いて靴箱にたどり着くと、それぞれの靴箱で上履きからローファーに履き替えて玄関に出て、「あ!とても風が気持ちい!」とおでこに当たる爽やかな風を感じます。
その間、リエはずっと俯いたまま一言も喋らず、ただ黙って私の後ろをついてきているだけでした。
私も何を話しかけて良いか分からないし、むしろ話しかけることが正解なのか分からないので、ただ黙って横を並んで歩きながら駅を目指して、少しひんやりとした風の冷たさを頬に感じています。
「私はこんな時に全く気が利かないなあ」と思いながら、2人で踏むアスファルトのジャリジャリという音を聞きながら、リエを気にしてない素振りをなんとか保ちながら周囲の景色をキョロキョロと見回します。
私たちの通っている高校は高台の上にあり、最寄り駅までの道を歩いていると眼下にズラッと並んだ住宅街が見えます。
夜になるとその住宅街の家々の光が灯り、街頭やビルの明かりでまるでダイヤモンドのように美しい風景が広がるのです。
だけど、高校生の私はそんな遅い時間まで学校に残っていることがないから、なかなかその景色は見れないんだけれど、いつか大人になったらそんなダイヤモンドのような夜景が見える家に住みたいなあと思うのです。
結局リエとは一言も喋らず解散したんだけれど、私はなるべくいつも通りの笑顔でいつも通り「じゃあね!」と手を振って挨拶をしました。
リエはやっぱり終始俯いたままで、「私に悪いと思ってるんだろうなあ」ということが見るからにうかがえます。
私は駅からさらに自転車に乗って家まで帰り、母親の作った晩ごはんを食べてお風呂に入り、ふかふかの布団の中で、まだリエのことを考えています。
向こうの居間からは父親が見ているテレビの光と音が漏れてきていて、少し安心しますが、リエに言われた「ずっと私のことが嫌いだった」という言葉がリフレインのように私の中で響いて鳴り止みません。
ギュッと強く目を瞑ると、目の奥に光を感じて、その光の向こう側に悲しそうに俯くリエの顔が見えるけれど、私はリエの肩に触れることも出来ないし、謝ったからと言って何も解決しないのは分かっているのです。
そんなことを考えている内に、いつの間にか深い眠りに落ちていて、私はうなされながら悪夢を見るのです。
私にとって、それは毎日のことで、今日はたまたまリエのことがあったから彼女が頭に出てくるのだけれど、毎晩見る悪夢が私を苦しめ、寝覚めは毎日最悪なのです。



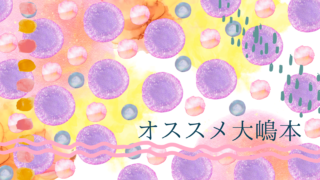







コメント