私はそれから高校生になって何人かの友達ができたけれど、孤独感は拭えないままでした。
なぜなら、誰かに本音を話しても分かってもらえているのかもらえていないのか、私には確認する方法がなかったからです。
一番仲の良い友達のリエと話したとしても、リエはいつもどこか上の空で「うん、うん」と笑顔でうなずいてくれるけれど、私は「もっとちゃんと話を聞いてよ!」とますます怒りが止まらなくなってしまうのです。
そんな時にリエが、私にあることを相談したいと言ってきました。
私は普段リエから頼られることがないから、ともて張り切って「どうしたの!?」と聞いたみたのです。
だけど、リエは恥ずかしいのかなかなか言葉にしてくれず、私はもどかしくなってついつい自分の話をしてしまうのです。
そうすると、リエはとても悲しそうな顔をしたので、私はお喋りをしていた口をつぐんでじっとリエの言葉を待ってみます。
私は黙って人の話を待つのが苦手なんだなあと、この時初めて気がついたのです。
「あのね、私ね、ずっとアンナに黙ってたことがあるんだ…」
そう呟いた彼女の横顔はとても美しく、夕陽に照らされて一筋の涙が頬を伝っていることに気づいた私は、慌ててリエにハンカチを差し出しました。
自分がくだらない話を長々して場をもたせようとしていたけれど、リエにとってはそんなことどうでも良くて、ただただ私を気遣わせまいとしているのか、空気を読んでいるのか。
「あのね、私…ずっとアンナのことが嫌いだったんだ…」
と小さな声で俯きながら呟いたのです。
私はちょっと驚きましたが、だけど心当たりはあったので、黙って話の続きを待ってみました。
また、2人の間には沈黙が流れて、とても長い長い時間二人の呼吸の音だけが聞こえるようでした。
私は今度は「どれだけ静寂が続こうとリエの話を遮らないでおこう!」と思っていたので、リエが再び口を開くまで、窓の外の傾く夕陽に目を向けながらその言葉を待っていました。




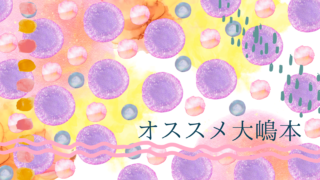






コメント