ある人が「自分はいつも、上手くいった!と思った時に限って、仕事で失敗をしてしまって、それまで築き上げてきた信頼を台無しにしてしまうんです」と落ち込んでらっしゃった。
その人は、もう泣く気力もないほど落ち込んでいて、「誰かに迷惑を掛けたくない」と、それでも自分以外の誰かのことを気にかけているのです。
私は、そんな心優しい人のために、「仕事での失敗をなくして、人から信頼されるスクリプト」を読もうと思いました。
それは、晴れた午後の昼下がりに、窓辺の背の低い本棚の上に、水差しがありました。
そして、その水差しの中には7分目ほど水が入っていて、1本の青々とした竹が窓から入るやわらかな風に吹かれて、ささやかに葉を鳴らしているのです。
すると、水差しの中の水が太陽の光に照らされて、キラキラキラキラと、床や壁に光を反射していてとても美しい。
だから私は、うっとりと光がゆらゆら揺れる影を目で追いかけます。
そんな時に、窓の外の遠くから子どもがはしゃぐ声が聞こえてきて、その瞬間、いっそう強い風がレースのカーテンを大きく揺らしました。
そうしてレースのカーテンが大きくパラシュートのように開くと、レースも太陽の光に照らされて、まだらな光と影の模様を床に映し出すのです。
でも、私はもしかしたら、何かをしないといけなかったのかもしれない、ということを突然思い出して、キラキラ、ゆらゆら揺れる床や壁の光と影から目を上げて、うーんと考え込みます。
そうやって眉間に力を入れて目を閉じて、何をしようとしていたのかを思い出そうとするのだけれど、窓の外の遠くから聞こえてくる、子どもたちの楽しそうな笑い声に思考が掻き消されていきます。
ああ、私もああやって本当は、無邪気に楽しそうに笑っていたいのにな、と少しあの感情が湧いてきそうになったのですが、再びゆらゆらキラキラ輝いている床の光と影を眺めていると、そんなことどうでよくなってきます。
そんな時に、本棚の上にある、写真立てがふと目に入りました。
なぜなら、その写真立ての中の写真には、青々とした笹を食べている竹やぶのパンダが一匹写っているのですが、私はそれをいつ、どこで撮ったのかを覚えていないのです。
そもそも、私は動物園に行ったことがあるのだろうか?窓の外の子どもたちのように、私は無邪気に楽しく子ども時代を過ごせていただろうか?と、あの子どもたちの楽しそうな声を聞きながら、私の過去を遡ってみるのです。
すると、たしかに私は動物園に行ったことはあるのだけれど、もしかしたらパンダを見たことがないのかもしれない、ということに気づいて、じゃあ、どうして本棚の上の写真立てにパンダの写真を飾ったのだろう?と新たな疑問が浮かんできました。
そうやって考えてみるのだけれど、いくら考えても私があの写真をそこに飾る理由は思い当たらないし、いつからそこに飾ってあったのか、私は毎日その窓から外を眺めて天気を観察しているのだけれど、覚えがないのです。
もし、1つだけ理由があるとすれば、過去に私のこの部屋に来たあの人が、こっそり飾っていったのかもしれない、と思い出すと、あの人の優しい声が、私の中に響いてくるような気がします。
そう、あの人は、いつも私の話をにこにこしながら黙って聞いてくれていたので、それまでの私は人から怒られることをとても、とても怖がっていたんだなあ、ということを今さら気づいたのです。
それから、あの人は私に、「人はそんなに怒らないよ」ということを教えてくれて、私のあの感情はいくらか落ち着いたのだけれど、床や壁にゆらゆらキラキラ漂うような光と影をずっと眺めていられるような、そんな生活を私はぼんやりと送っていたいと思ったのです。
そして、あの人が最後に私の家に来てから、かなりの年月が経ったのですが、あの人の声や言葉は時おり私の中でふわっと湧いて出ては、泡のように消えていきます。
それは、あの人が私の前から唐突に姿を消したあの時と同じで、だからもしかしたら、あの人は人魚姫のような、あしながおじさんのような人だったのかもしれないなあと思っているのです。
そうやって、あの人の存在が私の中に湧き上がるたびに、私の中に優しくてあたたかい光が広がっていって、私の手や指先や、お腹や足先まで冷えきっていたことに気づかされるのを、目を閉じて感じます。
そして、次にそっと目を開いた時に「さっきとは違う世界になっていたらなあ」と期待するのですが、何も変わらない現実が見えてきた時に、心の目であの人の優しくてあたたかい声を思い出してみると、またうっとりと眠たくなってくるのです。
そんなことを何度も何度も繰り返しているうちに、私はひとつ大きなあくびをして、伸びをすると、まるで長い夢から覚めた時のように頭がスッキリとしていることに気づきます。
それは、今まで見ていた現実がまるで夢のように忘れてしまうわけではなくて、今まで見ていた現実という悪夢が、あの人の声や言葉を思い出すたびに、優しい思い出に変わっていく感覚なのです。
なぜなら、あの人はいつも真っ黒い影のように私をあたたかい腕で包み込んで、こう言ってくれたから。
そう、「君はいつでも1人じゃないよ」と。
けれど、その時の私は、その言葉の意味が分からなくて、あの人にあの感情をぶつけてしまったのだけれど、それもまた、優しい思い出に変わっていくのです。
だから、目を開けても、私の目の前には淡い太陽の光を映した水差しの影が、キラキラゆらゆらと床を照らしています。
そして、窓の外から聞こえてくる子どもの声は、昼寝の子守歌のようで、私は座椅子に座ったままそっと目を閉じます。
すると、瞼の裏に、キラキラゆらゆら、あの影が私の中を照らすように揺れるのです。
ひとつ、爽やかな空気が頭に流れてきます。
ふたつ、身体がだんだんと軽くなってきます。
みっつ、大きく深呼吸をして頭がすっきりと目覚めます。







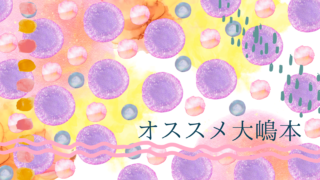



コメント