リエがずっと私の顔色を窺って私の後ろにくっついてきていたことは知っています。
なぜなら、リエにあーしたいこーしたいと言われたことが一切ないから。
リエはいつも私の言葉に従って動いてくれていたけれど、私はそんなリエを信用できなかったのです。
「どうしていつも私が決めなきゃいけないの!」という怒りで私の中はいっぱいいっぱいで、だからリエの本心を知りたかったのだけれど、私もリエに嫌われれるのが怖かった。
きっとこの時点で私たちは「友達関係」ではなく「主従関係」になってしまっていたのかもしれない。
そう思うと、私は急に怖くなってきたのです。
「私はリエをコントロールして言うことを聞かせようとしていたのかもしれない…」という自分が見えてきた時に、私は自分をとても恐ろしい人間だと感じてしまったのです。
私は、自分の部屋の窓から見える風景がとても好きです。
西日が強く射し込むこの部屋からは朝陽が見えないけれど、山の向こうに沈んでいく太陽を眺めていると、今の私の悩みなんかよりも「美しい」という気持ちが自分の中にあふれてくるから。
私は決してリエのことをバカにしているとか見下しているわけではなかったけれど、いつも私の言うことを聞いてくれるリエに対してどこか母親のようなものを求めてしまっていたのかも…と反省と後悔の気持ちでいっぱいになってきます。
リエはいつも何も言わず笑って私の話にうなずいてくれていたけれど、私はリエのその気持ちに応えられていなかったのだろう。
自分の甘えた気持ちを戒めるために、真冬にも関わらず私は部屋の窓を開けて冷たい空気を部屋の中に入れてみる。
だけど、その空気を冷たいと感じるどころか心地良いと感じてしまうのは、リエへの気持ちに支配されそうになっていた自分の感覚が自分に戻ってきたからかもしれません。
気づかない間に私の目からは大粒の涙が流れてきて、頬を伝っていきます。
夕陽が窓の外に見えていて、どんどん山の向こうへと落ちていき、やがてあたりが暗くなっても、私は部屋の電気を点けずにただぼんやり暗くなった窓の外を眺めていました。
隣の部屋からは父親のテレビの音が聞こえてくるけれど、私は無音のまま自分を罰するように、ただただベッドの上に座って今までのリエとの思い出を反芻しています。
どこから間違っていたんだろう?
いつから私はリエを母親代わりとしてしまっていたんだろう?
どうして私はリエの気持ちに気づいてあげられなかったんだろう?
いろんな疑問が湧いては消えていくけれど、答は見つからないまま時間が過ぎていきます。
そうこうしているうちに母親の「ご飯できたわよー!」という声がドアの向こうから聞こえてきて、私の思考が現在に戻ってきます。
父親も母親もこんな私を知らない。
両親に自分がどう映っているのか分からないけれど、私は黙って食卓に下りていき、ほかほかのご飯を口に頬張る。
あたたかくて美味しいご飯とは反対に、自分の心が冷めきっているのを感じます。
母親も父親もご飯を食べている時は一言も喋らないので、私も何も言わずご飯を平らげて、そのまままた自分の部屋へと引っ込んでいきます。
「明日リエに会ったら何て声を掛けよう…」と今頃不安になってきます。
リエを目の前にしている時はこんな不安なんて全く感じなかったのに、どうして今頃心配になってきてしまったんだろう…。
私は明日リエに会うシチュエーションを色々考えてシュミレーションしてみました。




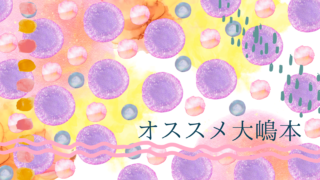





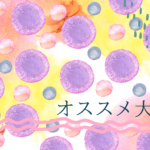
コメント