「毎日って、気づいたら早く過ぎているよね」とある人が言っていました。
その人は、1日1日が嫌なことがあって「早く明日になればいいのに」と思って過ごしているんだけど、気づいたらもう半年も経っていて、「何にもしていないのに時間だけ過ぎていく!」といつも焦っていたんです。
だから、私はその人に「ダーツ」の話をしてみました。
けれど、私もそんなにダーツは詳しくないので、まだ学生だった時に、夜の薄暗い照明の中のゲームセンターで、友達とあの黒や赤の円がたくさん描かれている的を狙っていたあの記憶を、頭の中から振り絞って思い出してみたんです。
そして、私はルールなんか知らないから、「とりあえず真ん中に刺さればいいのかな?」と思うんだけれど、後になってさまざまなルールがあることを知って、けれどざわざわと人の声が形を成していない言葉で耳に入ってくるゲームセンターや夜の繁華街はとても好きだったんです。
なぜなら、そこにいると私自身が何者でもないような気がするので、名前を持たない1つの個体としてあの雰囲気に溶け込めているようなそうでないような、そんな曖昧な空気は、夜の繁華街のヤニで曇った空や湿っぽい夏の深夜の静けさが私の肌を覆うのです。
だから、私は友達とダーツをした時に、何をどうすれば勝てるのか分からなかったので、とにかく「真ん中に当てよう!」と思って真ん中を目指して投げるのだけれど、いつも思ったところに飛んでいかなくて、真ん中よりかなり下の的ギリギリに刺さったり、そもそも的から外れて床に落ちたりしたんです。
すると、友達もみんなダーツが上手だったかどうか今の私の記憶には残っていないのですが、私は夜のゲームセンターのざわざわする感じが好きだったので、いつまでもそこにいたいなあと思って、窓のないタバコくさいあの部屋で、友達の声も聞き取りにくいんだけれど、それさえも私の頭をぼんやりと何か心地良い感じにさせてくれたのです。
けれど、いつかはここから外に出て、早朝の太陽の光を浴びないといけなくて、暗い部屋から明るい外に出た時の眩しさや太陽の明るさが苦手だったんだけれど、朝の爽やかな風が頬や半袖から出た腕に当たるのはなんとなく好きだったので、「早く帰って寝よう」と徹夜明けの頭を無理やり起こしながら始発の電車に乗って帰っていました。
そして、家に着くと、窓からはさんさんと太陽の光が降り注いでいて、私は眠たかったんだけれどもう少しその風景を眺めていたいと思って、レースカーテンに近づいて窓を開けると、ぶわっと風が部屋の中に舞い込んで、そしてベランダの柵の向こうに青々とした田んぼと畦道が見えるのです。
それから、窓を閉めていた時や電車で帰っていた時は眠くて気づかなかったのか本当は聞こえていたのか分かりませんが、窓を開けた瞬間に蝉の鳴き声が一斉に私の耳に飛び込んできて、それも一種類ではなくいくつもの夏の虫の声が大合唱のように私の眠たい頭を起こしたんです。
そうやって、夏に窓を開けてその空気を感じるのは今日がはじめてではなく、夏が来るたびに何度も何度もこの風景を目に焼き付けようと窓の外の景色を眺めるのは、それが私の田舎と似ていたからかそうではないのか。
なぜなら、私はあの田舎がそれほど好きではなかったので、子どもの頃はずっと早く大人になって都会に出たい出たいと思っていたので、あの田んぼの畦道も誰もいない夏の蒸し暑いアスファルトの照り返しも、ミンミンうるさく鳴く蝉の声も、今こんなになつかしくて愛しいものだと思わなかったんです。
だから、田舎の畦道を見るたびに、あの日の私が自転車で通ったガタガタいう砂利だらけの道を思い出して、そのたびに夏休みの1人退屈に過ごした長い休暇を思い出し、たしかに1人だったんだけれど、あの頃の私は本当に孤独だったのだろうか?
そして、少し大きめの小さな石を自転車で乗り越えるたびにサドルに振動がきて、小さく体が上下にバウンドするんだけれど、あのガタガタする砂利道を通っている私はなんだかとても好きで、たしかに運転しにくかったんだけれど、私はあの道を通るのが好きだったので、何度も何度もガタガタといわせながらあの道を自転車で走っていたのかもしれません。
そうやって、大人になってから思い出すあの頃の思い出はちょくちょくあるのですが、思い出の中の私はいつも1人で、いつもあの夏の風景で、あの頃私は何を考えていたのかもう思い出せないんだけれど、あの夏の空の青さや太陽の眩しさを思い出すたびに、なつかしさで胸が熱くなるんです。
そして、自転車を漕ぐたびに回るタイヤの音とアスファルトを走る音が静かな住宅街に響く時、私はなんだか「生きてるんだなあ」となんとなく思ったりもするんです。
そして、誰もいない夏の田舎の道路を1人、炎天下の中麦わら帽子が飛ばされないように気をつけながら漕ぐ私の自転車は、どこに行くのかをはっきり決めていなくて、ただひたすらこの天気の良い日にずっと自転車を漕いでいたいと思って、腕ににじむ汗や顔に照り付ける鋭い陽射しが、暑さ以上に何かを私の中で掻き立てていきます。
すると、大人になった私は、頭の中であの頃の思い出を思い出す時に、いつの間にか子どもの私ではなく大人になった私の姿で自転車に乗る姿がイメージされているのに気づくかもしれません。
そうやって、あの自転車がガタガタいう畦道や、両耳からつんざくような蝉の声が聞こえてくる田舎の静かな昼下がりを、大人になった私がもう一度そこに行った時にどう思うのだろうか。
そして、あの頃の私が感じていたことと今の大人になった私が感じていることは、もしかしたら違うのかもしれないし同じかもしれないけれど、それを証明する術もなくて、でもただあの夏の太陽の眩しさだけは今も変わらないような気がするので、だから私はどれだけ暑くてもあの風景を確認したくなって、眩しい昼下がりに窓を開けて蝉の声や真夏の陽射しを肌でじっとりと確認するのでしょう。
ひとつ、爽やかな空気が頭に流れていきます。
ふたつ、身体がだんだんと軽くなっていきます。
みっつ、大きく深呼吸をして頭がすっきりと目覚めます。

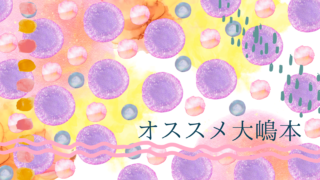






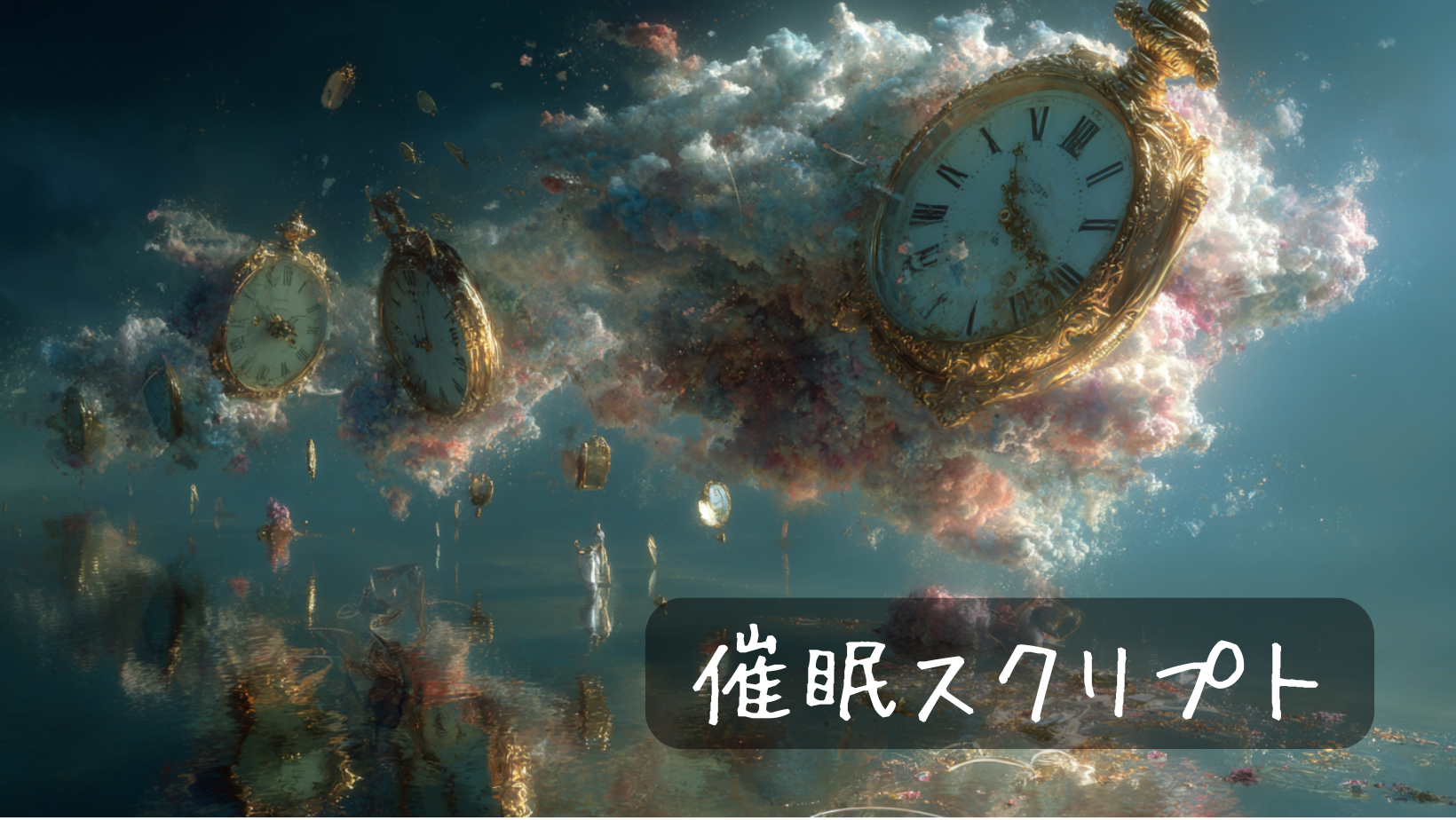


コメント