ある暑い夏の昼下がりに、探してたわけではないけれどすぐそこにあった自販機で、缶コーラを買ったんです。
そして、コーラ缶のタブを指でぐいっと引っ張ると、プシュッと炭酸の音がして、空気中に溶けていきました。
それから、口をつけてぐいっと喉に流し込むと、しゅわしゅわとした泡が私の喉を刺激していくのです。
そうやって、ごくごくとコーラを飲みながら仰ぎ見ると、空にはギラギラと太陽が輝いていて眩しいから、私は薄目になって、それでも空に白い光をらんらんと放つ太陽から目を逸らそうとしなかったんです。
すると、瞼を閉じてもその光は瞼の裏で燃えていて、どこかで蝉の鳴く声がせわしく聞こえてきます。
そして、あちこち聞こえてくる蝉の鳴き声に耳を傾けていると、ツーッと1本、2本と湿った肌の上を流れる汗の筋を感じることができます。
こうやって、暑さでぼんやりとした頭のまま、ジリジリと焼け付く太陽の陽射しを浴びて、手には水滴のついたコーラ缶を持っていると、ひんやりと指先が冷やされていって心地良く、熱気で視界が揺れるのです。
すると、向こうに見えていた自販機がぐにゃりと歪んで、まるで世界が回っているのか私が回っているのか、蝉の声が四方八方から聞こえるこの道路がまるでコンサート会場のようで、上も下もわからず私は回転します。
そして、平衡感覚を失ってぐるぐると収縮しながらどこかへ落ちていったあの暗闇は、どこかに繋がっているのかいないのか、私は回りながらどこかへ落ちていく。
そうやって、長い時間だったのか、あるいはほんの少しの時間だったのかわからないけれど、私が着地したのは暗い洞窟の底でした。
それから、上を見上げると、はるか上の方に出口の穴があって、そこからうっすらと光が射しこんでいて、私がいる地面を淡く照らしていて、穴の向こうの空高くを数羽の鳥が何か鳴きながら飛んでいく影が見えます。
そして、その鳥たちが去った後には暗闇と静けさだけが残り、穴の向こうでは森の中のざわざわという音が不気味に響いているのだけれど、ここは誰もおりてこられない、安全な聖域だと知っているのは、月の光で淡く照らされている私の手や足がほんのりとあたたかいからなのかもしれません。
だから、私はいつもこんな暗闇に落ちた時に考えるのが、まだ幼い頃に踊っていた「舞」なのです。
なぜなら、あの舞は、黒地に蝶の絵柄がきらびやかな扇子を持って舞うのだけれど、障子の向こうから見たその舞の影はとても美しく、まるで実家にあった金箔の屏風の中の虎が現実のものになったように、なめらかに艶めかしく舞うのです。
そして、その舞は音もなく舞うので、桜が枝からひらひら舞い落ちるあの音よりも軽く、小石が風にコロコロと転がされるあの音よりも儚く、舞うのです。
そうやって、顔が見えない踊り子は影のまま、誰かのために舞っているのか、自分の存在がここにあることを誰かに知らせたいのか、左右の手を交互に振り上げ、両脚をしなやかに上げたり下げたりするのです。
それから、舞を踊っているのは私の意志なのか、それとも誰かに踊らされているのかわからないけれど、障子の向こう側で舞う私、もしくは女性の影は、どこでその踊りを覚えたのか。
そうやって、音もなく踊る踊りを誰に見せるわけでもなく、はらはら舞い散る紅葉やイチョウの中でも、やはり絶えず踊り続けるので、いつしか季節は秋から冬になり、雪が積もり、庭にはしんしんと真っ白い世界が広がっていたのです。
それでも、踊り子は踊りをやめようとせず、母の形見の黒地に蝶のきらびやかな扇子を片手に、障子の向こうで踊り続けるんだけど、その踊り子はいくら汗をぐっしょりかいていても、踊ることをやめようとはしなかったのです。
そして、それは踊り子しか知らないことで、踊り子はもしかしたら自分が踊りをやめてしまったら、季節が移り変わらなくなってしまうと思っていたのか、母を忘れないために踊り続けていたのか、踊り子にももしかしたらわからないかもしれないのだけれど、1つ1つ床につくたびに爪先の感覚を感じながら、キラキラ輝く扇子を上にしたり下にしたり、忙しく動かすのです。
やがて、季節は春になり、すべての雪が解けて蕗の薹が芽吹き、竹が顔を出し、紋黄蝶が庭を飛び始めた頃、それでも踊り子は舞をやめずに、蕾が大きくなっていくにつれて、その舞も身振り手振りを大きくしていくと、今までよりも少しだけ、着地の時の足音も大きくなっていくのです。
すると、梅雨の時期が過ぎて、太陽がさんさんと輝くあの夏の日になった頃に、いつか舞姫が自販機で買ったコーラ缶のことを思い出し、あの缶を自販機から取り出す際のひんやりと冷たい感触や、缶の表面についた水滴の心地良さを思い出します。
ああ、そうだ、私はこの衣装を脱いで、白いTシャツにジーパンを履いて、炎天下の中を歩いていたんだ、と思い出すと、またあの道路を歩きたくなったんです。
そして、それはなんでもない日常の1コマで、毎日学校に行ったり、スーパーに行ったりするあの道路で、彼女にとってはなんでもない道なんだけど、でも彼女にとっては大切な日常の1コマで、あの変わらない日々が美しいと今になって思い出す時、私の脇を通る車の音や、ペタペタというサンダルの音までリアルに思い出すことができるのです。
そうやって、あの頃はなんでもなかった毎日が、輝かしい日常の1ページに刻まれていることを、私はあの太陽を思い出すたびに、あの光を、あの暑さを、胸に刻んで生きているのです。
ひとつ、爽やかな空気が頭に流れていきます。
ふたつ、身体がだんだんと軽くなっていきます。
みっつ、大きく深呼吸をして頭がすっきりと目覚めます。







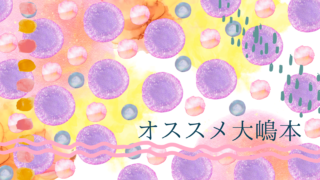
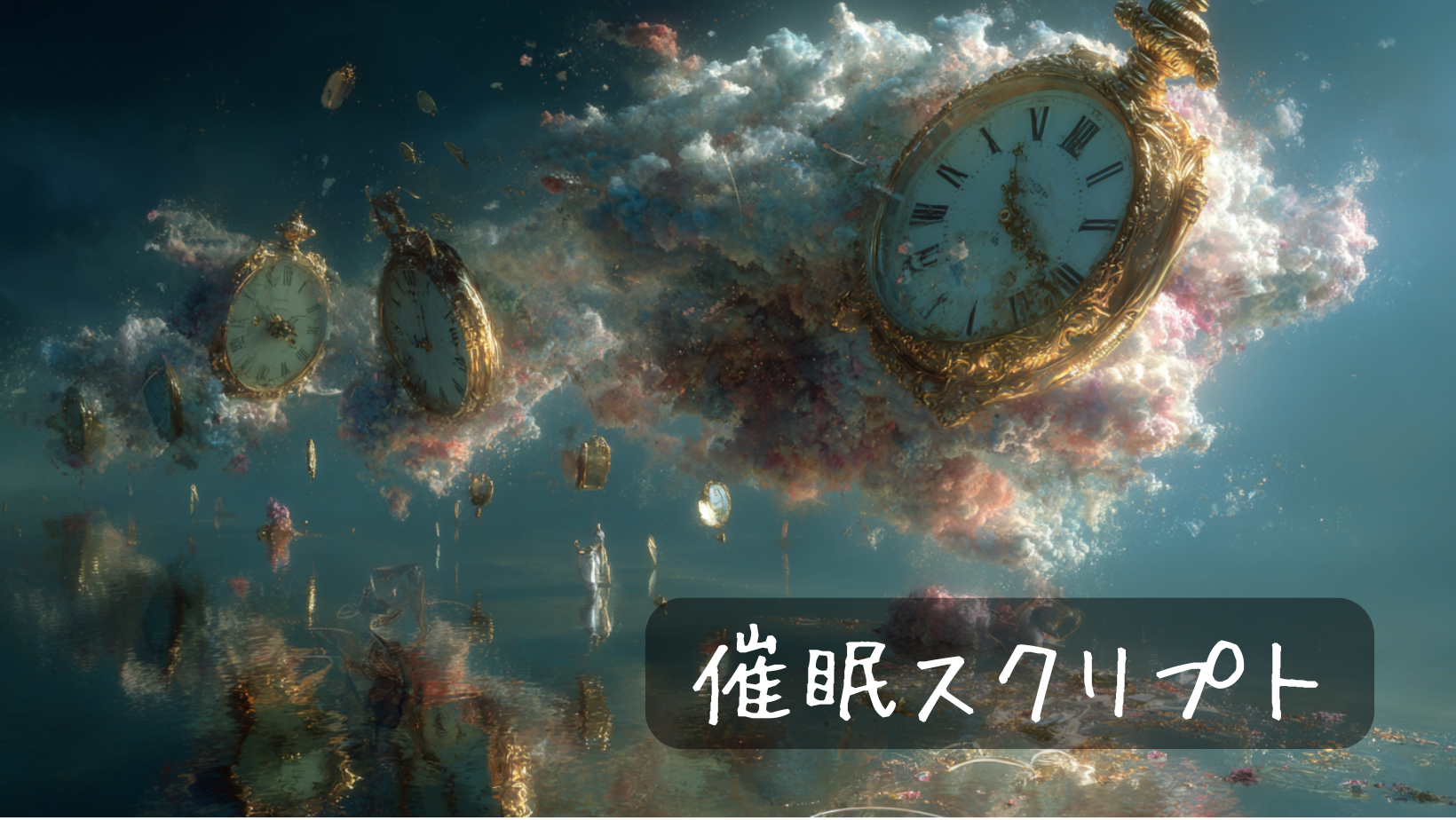
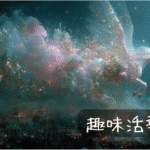

コメント