ある人が、「自分の中にはいつも2つの物語があって、どっちの話もリアルなんだ」と教えてくれた。
それはどんな話?と聞いてみると、その人は詳しく2つの物語について私に教えてくれたんだ。
その人はプラレールが子どもの頃から大好きだったから、プラスチックの青や黄色の線路を組み合わせながら、電車がぐいーんと線路を進んでいく様子を眺めるのが好きだった。
その一方で、子ども部屋の外から母親のあの声が聞こえてきた時、体を固くしてじっとしていたんだっけ。
じっと自分の腕で自分の脚を抱えていると、腕のぬくもりが脚の表面に伝わっていって、じんわりとあたたかくなる。
そうやってあの声をやり過ごしながら窓の外をなんとなく眺めてみると、青い空に白い雲が流れていて、「窓から見る空は狭いなあ」なんて思った。
窓の外にはスズメが電信柱にとまっている様子が見えるから、その人は頭の中でスズメの囀りをイメージしてみたんだ。
何匹かのスズメがバラバラのタイミングでチュンチュンと鳴いているのは、まるでショパンのワルツのようで、心臓が楽しさと一緒にトクトクと脈打つ感覚を感じるのです。
「あの鳥のように、大空を飛べたらなあ」と思うけれど、自分の翼では上手く風に乗れずに不安定になって、傾いて落ちてしまうのではないかと思うと、美しい空をこうやって地上から眺めているだけで良いような気がしてきた。
もし、空の向こうまで飛んでいくことができたなら、どんな声で歌う鳥に会うことができるだろう?
その鳥はフラミンゴだろうか?それとも、カナリアだろうか。
いろんな鳥の声が私の中で響いた時に、その人は1つ大きなあくびをした。
「そう言えば、お腹が空いたね」とその人は言ったので、私のお腹がぐうと鳴って、ほんとだ、私もお腹が空いているんだと思い出したようにお腹をさすってみた。
その人はプラレールの話を忘れてしまったようで、ある休日に両親に連れていってもらった渓谷の秘境のお団子屋さんの話を始めた。
そのお団子屋さんは山奥にひっそりとあって、真夏に行ってもひんやりと涼しい風が吹いているから、家族で並んで赤い布が掛けられた椅子に腰かけながら、そばを流れる小川の音に耳を澄ませながらお団子を無言で食べていたこと。
小川がちょろちょろと流れていく様子は、眠れない夜に聞く子守歌のようで、お団子を頬張りながらぐっすり眠れそうな心地良さを感じていた。
両親はその頃、とても仲が良くて、「僕なんかいなくても良いんじゃないかな」と、その人は2人の顔を交互に見上げながらある感覚を感じていた。
でも、その感覚を両親に伝えたところで何も解決をしないことを知っていたから、その人は黙ったままお団子を食べて、お団子屋の上に被さるように枝を伸ばしている青いふさふさの葉がこすれる音を聞いていた。
その音はさざ波が寄せて返す音にも似ているような気がして、そういえば最後に海に行ったのはいつだっけかなあと、目を閉じて記憶の中を探ってみる。
記憶の中の海は太陽の光をキラキラと反射させていて、その光の玉が幾重にもなって海の上を踊っているようだった。
海は良い。
瞼を閉じて耳を澄ますと、波の音が1つではないことに気づく。
大きな波の音の合間に、小さな波の音が折り重なって空気を震わせ、絶えることなく静寂を破っていくのだ。
じっとりと湿った潮風が額や頬や腕を撫でていく。
遠くでカモメの声がしたような気がしてハッと目を開けると、相変わらずそこには海に沈んでいく大きな白い太陽があった。
太陽は海も空も私の肌も白く照らして、やがて来る闇に負けないようにと一際強く光を放っているのか、その光に吸い込まれていくようにカモメの大群の声が遠ざかっていく。
何も変わらないようで不規則に、波は一定のリズムを刻みながら、私の足元まで届くのか届かないのかというところまで寄せてきて、追いかけっこのように戻っていくから、あの人とかけっこをしたあの日のことを思い出したんだ。
あの人が、夕焼けでオレンジ色に染まっていく街の中で「捕まえてみてよ!」と笑うから、私はその人の背中に手を伸ばすと、その背中に触れるか触れないかというところでその人はひらりと逃げていく。
その人はいつも笑っていたけれど、その時は逆光で彼の顔が半分隠れて見えたから、私は急にある感覚に襲われたけど、あの人と同じように笑うとなんだか楽しいような感じがしてくるから不思議なんだ。
あの人が走ったアスファルトを同じように駆けていくと、あの人と同じものが見えるのかな?とワクワクしてあの人の見えない足跡を辿って行ったけど、途中で見失ってしまった。
夕暮れの街は急速に影を増していくから、アスファルトに伸びていた私の影も夜の闇に飲まれていってどこに行けば良いのか分からなくなった時、遠くて犬の遠吠えを聞いたんだ。
あの感覚が襲ってきそうで心細かった時に、犬の遠吠えが聞こえる方へ急いで走っていくと、もしかしたらあの人がそこで笑ってまっていてくれるような気がしたから、ほんのわずかな希望に縋るように、速く、速く走った。
だけど、走っても走っても闇は尽きることなく私を追ってくる。
黒いアスファルトは黒いままで、どこまで前へ進んでも黒は黒だった。
犬の遠吠えはまだ聞こえるけれど、一向に距離が縮まったような気がしないのは、アスファルトがランニングマシーンのようにぐるぐると回っているからかもしれない。
私はどこへ行こうとしているのか、どこへ行きたいのか、あの人に追いついて何をしたいのか分からないまま、がむしゃらに走って、自分の乱れた呼吸を聞く。
心臓の音が大きくはやくなっていった時に、ようやく私は「生きている!」と思ったんだ。
1人で走っているだけなのに、今、生きている!
この真っ暗な世の中に私だけしかいなかったとしても、走って荒くなった呼吸を感じるたびに、あの感覚が私の中から湧き出てくる。
ひとつ、爽やかな空気が流れてきます。
ふたつ、身体がだんだんと軽くなってきます。
みっつ、大きく深呼吸をして、頭がすっきりと目覚めます。
―――――
本日は、【無意識さんの力で無敵に生きる】より、“自分の中のジオラマ”をテーマに催眠スクリプトを書いてみました。

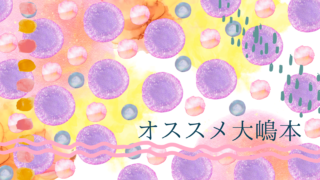










コメント