「催眠」を用いて独特な手法でさまざまな患者の症状を治療してきたミルトン・エリクソン博士。
そんなエリクソン博士の逸話がたくさん紹介されている【私の声はあなたとともに】。
何度読んでも見事なリフレーミングで、読んでいる私の心と頭までほぐされていきます。
今回はそんな本書について語っていきます。
どんな本?
1996年10月に二瓶社から発売された本です。
エリクソンと交流があった精神科医のシドニー・ローゼン氏が、エリクソンの「教えの物語」を集めたのが本書です。
シドニー・ローゼン氏は一時期日本に滞在されていたことがあり、日本語版の本書の一番最初に【日本語版への序文】として、日本人の我々へメッセージを書いてくださっています。
その序文だけもう胸がいっぱいになってしまって、ローゼン氏のメッセージを読んだだけで、この本は優しく愛に満ちた本なのだと確信しました。
私が以前にこの本を読んだ時は、現代催眠を学ぶ前でした。
催眠をある程度知ってから読んだ今回、改めてミルトン・エリクソンの素晴らしさを実感しました。
読もうと思ったきっかけ
自分が主催している読書会『心の栄養読書会』の課題本として、私の中指が選んだのが再読のきっかけです。
そして、最近は「毎日、催眠スクリプトを1つ書くチャレンジ」を勝手に自分の中で行っていたのですが、毎日書いているとだんだん似通った言葉やイメージばかり出てくるのが気になっていました。
過去、大嶋先生に「明るいイメージ、暗いイメージと考えてる時点で意識的になってるよね」と教えていただいてから、「これは悪いイメージかも…」と考えることをやめて頭に出てきたままを書くようにしていたのですが、それでも毎日書いていると「この表現、昨日も書いたしな」とか気になってきていたんです。
催眠スクリプトの書き方を迷走していたというか、慣れてきた頃のある種のスランプと言いますか…。
そんな悩みを突破したくて、意気揚々と再読し始めた本書。
とても…とても良かったです。
ここでぜんぶ言っちゃうと美しくないかなあと思いますが、大嶋メソッドを勉強してから読むと「あ!これの元ネタはもしかして…!」というエピソードがたくさん含まれています。
大嶋先生がエリクソン博士やお師匠さんを心から尊敬されていることも改めて見えてきて、二倍感動しました。
【ネタバレあり】心に響いた3選
まだ読んでいない人への注意事項
この本の中には、100以上ものエピソードが出てきます。
その中でも特に私のお気に入りのエピソードを3つ紹介させていただきます。
エピソードは私流に端折って書かせていただくので、詳しくは本書をご覧ください。
素晴らしいです。
また、エピソードのどこに私の心を動かされたのかを書く過程で、エピソードのネタバレがあります。
純粋な気持ちでこの本の中のエリクソンが起こした奇跡を読みたい方は、以下のレビューは読まない方が面白く読めるかと思います。
シナモンフェイス
『リフレーミング』の章で出てきたエピソードです。
ある時に、他人のことも両親のことも兄弟のことも同級生のことも自分のことも大っ嫌いな娘をなんとかしてほしいと、あるお母さんがやってきました。
そのお母さんは以前、エリクソンに痛みの治療をしてもらったことがありました。
なぜ女の子はそんなにも嫌うのかというと、女の子の顔中にそばかすがあるからです。
エリクソンはお母さんに、車の中にいて中へ入ってこない娘を強引にでも連れてきなさいと言いました。
そこまで強引にしなくても女の子は中へ入ってきて、エリクソンがいるドアの前に立ってエリクソンを睨みつけていて「やんのかこら!」という姿勢でした。
すると、その女の子の姿を見たエリクソンが「泥棒!泥棒だ!」と言います。
女の子は「私は何も盗んでない!泥棒じゃない!」と言います。
しかし、エリクソンは「いや、君は泥棒だ。何を盗んだか知っているぞ。証拠だってある」と言います。
そう、エリクソンは台所で女の子がシナモンクッキーやシナモンパンやシナモンロールの入った缶に手を伸ばしたな!と言って、「それで、顔にシナモンがこぼれたんだ」と女の子に言います。
【シナモンフェイス】の誕生です。
女の子は、シナモンのパンやクッキーが好きだったので、自分のそばかすに新しく名前をつけました。
なんとも素敵なリフレーミングじゃないですか!
シナモンフェイスという名前、私も大好きになりました。
また、エリクソンがはじめに「泥棒だ!」と言ってわざと敵意や怒りを強めたため、女の子の心の中に空白ができました。
そうすると、好意的に反応できる心の枠組みが生まれます。
その他にも、この短いエピソードの中には、エリクソンのたくらみがいくつも散りばめられています。
90歳でも果物の木を植えて食べられるのを待つ父
『自分の人生を引き受けること』の章の一番最初の話、【死および死ぬことについて】ではエリクソンの父の話が出てきます。
エリクソンのお父さんは、97歳と6カ月で亡くなりました。
それまでに何度か心筋梗塞の発作を起こして入院していたのですが、そのたびに「また無駄に過ごしてしまう」と入院生活を嘆いていました。
そんなお父さんは、96か97歳の時に果物の木を植えたそうです。
その木に実がなって食べられるまで生きるつもりで植えたそうです。
この話を読んで、私はガーン!とショックを受けました。
私は、エリクソンのお父さんのまだ半分も生きていません。
それなのに、もうずっと死ぬことについて考えてばかりいて、毎日を生き急いでいました。
それは高校生の時から、いや、小学生の時からだったような気がします。
「今日も何もできなかった…」「もっと意味のあることをしなければ」と毎日思っているわりに、何も成し得ていないと焦って40歳間近まで過ごしてきました。
それなのに!エリクソンのお父さんは、100歳近くになっても植えた果物の木の実を食べるつもりでいるのか!?
私がもし96とか97歳だったなら、「どうせその頃まで生きていない」と思って、もっと成熟の早いものを植えるか、そもそも諦めて植えないと思います。
エリクソンの父は、なんと未来志向なのか!
また、このエピソードの中でエリクソンは
私は、人は産まれたその日が死に始める日だと、心に留め置くべきだと思っています。少数の人は、死ぬことにそれほど多くの時間を費やさず人生を有効に生きているのに比べて、多くの人は死ぬことを長々と待っています。(p175)
と言っていました。
前回書いたレビューの【夜と霧】もそうでしたが、私はどんな人生を生きたいのか?を改めて考えさせられるエピソードです。
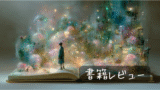
何でも便利になって、望めばすぐ手に入るようになった今の時代。
多くの自己啓発本にも書かれていることですが、もっと自分の内面と対話して、いずれ訪れる死を怖がって待つよりも、避けることができないいつか来る死までに何をやりたいのか?自分の心に聞きながら毎日その一瞬一瞬を過ごしていきたいですね。
立ちすくむ患者
『精神病患者の治療』の章に出てきたエピソードです。
7年ほど病棟のまわりで立ち尽くしていた患者がいました。
その彼は一切話をせず、しかし誰かに言われれば寝て、必要ならお風呂に入ります。
それ以外の時はたいてい立っていました。
誰が彼に話しかけても反応がなかったのですが、そこでエリクソンは確実に彼が反応するように仕向けます。
彼に床磨きをさせようとするのです。
エリクソンは彼のところへ床磨きを持っていき、彼の指にその柄を巻きつけます。
でも、彼は立ったままでした。
毎日エリクソンは彼に、「床磨きを動かしなさい」と言います。
ある時に、立ったままの彼は1インチずつ床磨きを動かし始めたんです。
それからもエリクソンは毎日彼に床磨きをするように言って、病棟全体をきれいにすることができるようになった彼は、やがて一日中エリクソンに酷使されるようになりました。
すると、その彼はエリクソンを責め始めました。
それに対してエリクソンは「もし何か他のことをしたければ、どうぞおやりなさい」と言ったんです。
エリクソン、さすがですよね!
それから床磨きの彼はベッドメーキングを始め、話すことも始め、病歴や妄想も語り、1年経たない内に働き出しました。
床磨きをきっかけに、外の世界と繋がり、適応できるようになったのです。
エリクソンの治療方針の1つに、【患者が自分からできるようになるまで指示する】というのがあります。
私も鬱の経験があるので、よく分かります。
あのどん底の時は何もしたいことが分からないし、何が自分にとっての“快”で何が“不快”なのかも分かりません。
だから、不快なことも知らずにやり続けていたりします。
大嶋先生の焼豚の話ではありませんが、めちゃくちゃ不快なことやものすごく絶望的なことがないと心が麻痺してしまっているので「嫌だ」という自己主張すら出て来ないんですよね。
「あれやりなさい」「これやりなさい」と人に指示されてやってみて、「おいおい、これは違うだろ!」と抵抗できるようになった時、鬱がやわらいできている兆しでしょう。
選択する能力は、患者がより健康になり始めていることの最初の兆候であった。(p211)
それはきっと【夜と霧】にでも出てきていた「能動的に生きる」ということとも関りがあるのだと思います。
ミルトン・エリクソンのいやしのストーリーを読んだ変化
私が大嶋信頼先生のメソッド「心に聞く」をマスターしたのは、ある先生のおかげです。
それまでは心に聞くをしていても、「これ本当に心の声?」と疑ってしまっていました。
自分がそう答えてほしいから、意識で望む返答が返ってきてるだけなんじゃないかと。
でも、カウンセリングをしてもらっている時に「じゃあ、一緒に心に聞いていきましょう」と先生が「心よ~、」と話しかけてくださったあの歌声のような声が、カウンセリングが終わった後に一人で心に聞く時にも脳内で再生すると、無意識の声を聞きやすくなった気がしていたんです。
だから、心に聞くが苦手な方には「自分の声で聞こうとせず、私の声が聞こえたままを繰り返してみてください」とお伝えしていたりします。
この本のタイトル【私の声はあなたとともに】は、エリクソンが催眠誘導を行う時に使うフレーズに因んでいるのだと思います。
エリクソンは誘導を促進するために、「そして私の声は、あなたのゆくところならどこへでもいっしょにゆくよ」というフレーズを使っていたそうです。
これは、エリクソンがトランス状態の患者とやり取りを保つためのフレーズであり、もう1つ、後催眠暗示の合図としても役立っていたそうです。
あるいは、「きらめく彩りが見えるでしょう」というフレーズもあったそうです。
すると、セッションのずっと後になってから後催眠暗示として患者は「きらめく彩り」を見るといつも、「きらめく彩り」の暗示と一緒に与えられた暗示に応じるようになる。
これは大嶋先生がお師匠さんの催眠を受けられた後のエピソードでもたびたび出てきますよね。
満天の星空だったり、チョコレートだったり。
私が大嶋先生の催眠スクリプトを聞いて「これは後催眠暗示だな!」とはっきり自覚できているのはさほど多くはありませんが、たとえばコロナ明けに開催された『無意識の旅感謝祭!』の会場で聞いた「ちいさい赤ちゃんのてのひらとなんかキラキラしている話」。
後に『無意識の旅』でも投稿してくださいましたが、あの物語だけ何回聞いても頭に入ってこなくて、いつもなんか小さいてのひらとキラキラしていることしか思い出せません。
だけど、あのスクリプトを聞いてから、私の中ではことあるごとに何かがキラキラキラキラしています。
また、大嶋先生の【催眠ガール】に出てくる「排水口に水が流れ込んでいく」あのイメージ。
夏目ちゃんが何か嫌なことがあった時に「排水口にザーッと流れていく」ようなイメージをしていましたが、私もあれを読んでから同じく排水口にザーッと水が流れてスッキリするようなイメージが脳内で再生されていました。
もしくは、これも大嶋先生の本になりますが【それでも大丈夫 不安を力に変える方法】に頻繁に出てきていた「〇〇になっても大丈夫!」。
あれを読んでからしばらくは、何かがあるたびに「〇〇があっても大丈夫!」「〇〇でも大丈夫!」とすぐ頭の中に浮かんできたものです。
僭越ながら、自分で書いた催眠スクリプトでも後催眠暗示がちゃんと入っているようで、スクリプトを書き終えた後にちらちらと頭の中に浮かんでくるイメージがあります。
これらの暗示には、命令や見方の変更が含まれていることがあるが、それらは、取り込まれた両親や超自我の声として(しばしばエリクソンの声で)「聞こえて」きた。(p29)
この治療者の声の取り込み現象はどんな精神療法でも起こるものですが、患者が催眠トランスに入っている時は極めて起こりやすいと述べられています。
アメリカ精神医学会のキュビー博士が、催眠のトランス状態では催眠療法家と被験者の境界がなくなると仰っています。
そして被験者は、催眠療法家の声を自分の頭の中から来るかのように――自分の声のように、聞く。(中略)彼の声はあなたの声になり、あなたがどこにいてもあなたとともに行く。(p29)
エリクソンは、両親からの命令暗示を後催眠暗示で新しい考えに少しずつ置き換えていっていました。
それはまるで、私が患者として催眠療法を受けていた時に、カウンセラーさんに大人に成長させてもらった時のようなあの感覚と同じなんだと思います。
私自身、いくつも催眠スクリプトを書いていて思うことがあります。
メタファーには際限がなく、同じ悩みでも違う物語を書くことができるということ。
そして、違うメタファーで違うストーリーを書いた時に、「こういう見方もできるんだ!」と気づかされます。
私が「私の」頭で考える時、それまでの暗示が邪魔してくる時がほとんどでした。
しかし、私の呪いの常識を破ってくれたのは、カウンセリングが終わった後にも心の内側から響いてくるカウンセラーさんの声であって、きっと私は「自力で」「1人で」踏ん張るのではなく、あの声の支えがあったからこそ、いつの間にか1人の足で立てるようになったのだと思います。
そこには、現実的に見える物理的距離は関係なく、離れていても私を信じてくれている人の存在を感じるだけで、あそこにはもう戻らなくても良いという暗示かもしれません。
いつか私の声も、誰かの人生をそっと見守り、自由に生きる糧になれたらと思っています。
そして、催眠のあの声にはきっと、無意識のやさしい声がわたしとともに、何があってもどこにいっても一緒についてきてくれるのです。
まとめ
勝手ながら、私はこの本に大嶋先生の原点をみたような気がしました。
たとえば、あちらの部屋まで行くのに何通りの方法があるのか?とか、相撲部を強くするようにライフルチームを鍛えるとか、夢の中で新しいパターンを見い出すとか、その他にもたくさん、ミルトン・エリクソン博士のことを学べば学ぶほど大嶋先生のメソッドも深く理解することができると思います。
どの学問もそうですが、催眠も学べば学ぶほどどんどん新しいことが出てきます。
ある程度学ぶと自分の中に常識が凝り固まってしまうのですが、催眠療法は常にフレッシュな視点を忘れず、枠組みに囚われない考えを持つ柔軟性が大切なんだと思っています。
それを忘れてしまいそうな時は、このエリクソン博士の話を読んだり、大嶋先生の無意識の本を繰り返し読むことで、また無意識の美しさを思い出しています。
さあ、私はエリクソンの父のようになるために、今から何ができるだろうか?
そんな人生への楽しみも一緒に思い出させてくれるはずです。
参考レビュー
この記事内に出てきた本を紹介した私のブログ記事のリンクを以下に貼っておきます。
👇ヴィクトール・E・フランクル【夜と霧】
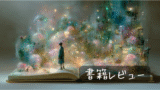
👇大嶋信頼【それでも大丈夫 不安を力に変える方法】

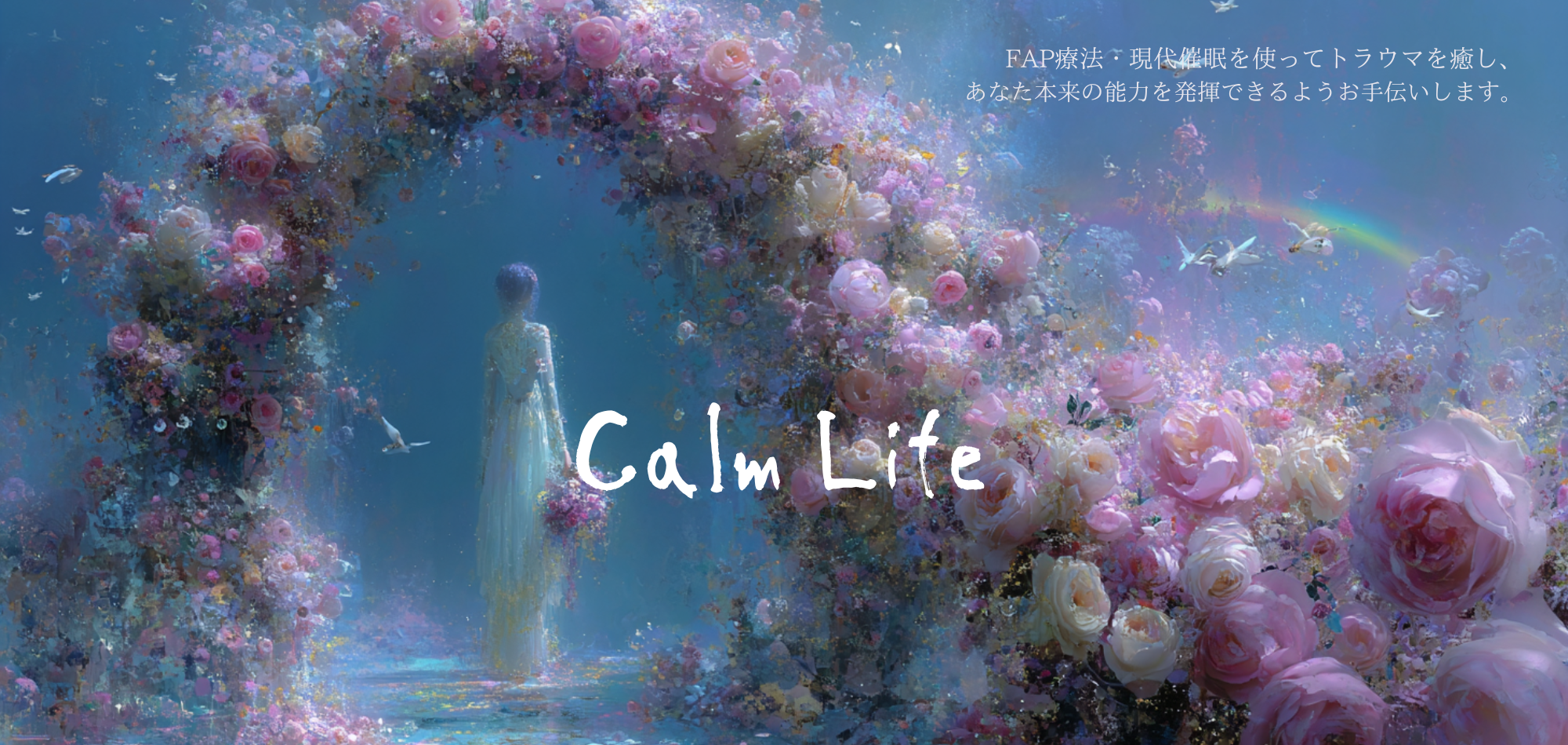
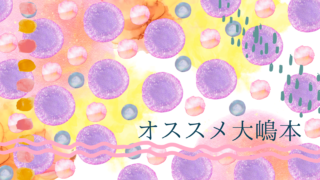










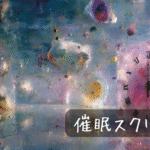
コメント