「人に間違いを指摘されるのが、とても怖いんです。もし間違いが見つかれば、私はもうこの世に生きていられないぐらい…」
そんなことを仰ったある男性に、小学生の時の体育館のステージで行った「舞台」のことを思い出してもらったんです。
そして、そこには大量のドライアイスがもくもくと焚かれていて、舞台の上は雲の上のように真っ白で、その中で1人、主役の男の子が大きな声で、誰もいない観客席に向かって台詞を朗読しています。
そして、あなたはその様子を舞台の下から眺めているのですが、自分の出番はまだまだなのに、今にも心臓が飛び出そうなぐらいドキドキしていたので、それがみんなに見つからないように、なるべく「ふつうの表情」をしておこうと思って、ぐっと頬や口元に力を入れました。
すると、自分の心臓の音が大きいのかそうではないのか分からないけれど、舞台の上の男の子の台詞がまったく頭に入ってこなくて、「あれ?今どこを読んでいるんだっけ?」と頭の中の脚本のページをペラペラめくって探してみるのですが見当たらなくて、体育館の窓から入ってくる太陽の陽射しのようにだんだんと頭が真っ白になっていったんです。
そうすると、何にも考えられなくなってくるので、なぜだか緊張がほぐれてきた気がして、だんだんと男の子の声がはっきりと聞こえてきて、その言葉が脳に届くと、「あ!まだここなんだ!」というのが分かって、安心してその台詞を聞いていることができるんです。
そして、男の子の台詞が終わって、男の子がピアノの伴奏に合わせて歌い始めた時に、そろそろ自分の出番が近づいてきたので舞台袖に移動すると、なんだかもわっと生暖かく埃っぽい空気が僕のまわりにまとわりついて、本番前の独特の緊張感と高揚感を高めてくれるのです。
それから、いよいよ自分の出番かもと思って誰もいない観客席を見ると、そこには太陽の眩しいくらいの白い光がさんさんと降り注いでいて、どこか懐かしいようなうっとりするような感覚に包まれます。
けれど、しっかりと前を見て頭をしゃっきりとさせていないとダメだ!と思って、窓から降り注ぐ光に照らされたパイプ椅子を眺めるのをやめて、舞台の真ん中で歌っているあの男の子に注意を向け直します。
すると、男の子がもくもくと焚かれたドライアイスの中に消えていって、明るくテンポの速い曲に変わったので、「さあ!自分の出番だ!」と思って舞台の中央へ駆けていくと、少し前につんのめりそうになったのですが、幸い僕の他にも10数人のみんなと一緒に一斉に舞台へ飛び出たので、僕一人が躓いたところで誰も気づかないし、それもまたある一つの風景に過ぎないのです。
なので、僕は大してそのことを気にせずに定位置につくと、僕の右ななめ後ろの人が始めのフレーズを歌い始めて、次に僕の左横の人が最初の人にハモッって歌い始めて…と、順番に1人ずつ歌に参加していくと、あちこちから同じ声量の声が聞こえてくるので、なんだか僕の立ち位置が曖昧になってくるんです。
そして、それはきっと、みんなとの境界線が今だけなくなって、みんなで1つのものを作っているという自信に繋がるのか、僕1人では出せない声量をみんなの声を重ねることでどこまでも届けられるのか、そう、僕の後ろの人と隣の人との境界線が曖昧になってくるので、「意識をしっかり持たないと」と思って舞台真正面にある体育館の開いている入り口に視線の一点を集中させるのです。
そうやって、視線を狙ったところに定めることによって、僕の意識はしっかりと保たれているのかそうではないのか、それははっきりとは分かりませんが、さっきよりもクリアに後ろの人や隣の人が歌っている歌詞が「言葉」としてきちんと耳に入ってくるので、境界線が曖昧でも境界線がクリアでも、安心できるものなんだなあと気づきます。
なぜなら、境界線が曖昧な時は、まるでみんなと1つの大きな生き物になってある大きなものを動かしているような気持ちになるのですが、境界線がクリアだと他人の立ち位置と自分の立ち位置がはっきりクリアになるので、立っている時にしっかりと自分の足の裏の感覚を感じていると、「自分」という存在をきちんと感じられるのです。
だから、私はきっと、ドライアイスがもくもくと私たちを覆ってしまったとしても、みんなで手を繋げば怖くないかもしれないし、自分1人でもその出口を見つけられるんじゃないかと思うのは、私がそれを「できる」と知っているからなんです。
なので、「できる」と知っている私は迷いなく煙が薄い方を目指して歩んでいけるし、目の前が霧のように真っ白で見えなくなってしまっても、後ろや横の人の声の位置から、私の正確な位置を知ることができるのではないかと思うんです。
そして、もし真っ白い煙の中で誰かが迷っていたとしたら、私は迷わず手を差し伸べようと思うのは、私がいい人だからなのではなく、迷った時のその人の気持ちが分かるからで、その迷っている人の掌をぎゅっと握り締めた時に、私の安心がその人にも伝わって、その人も幾分か気持ちが楽になるのかもしれません。
そうやって、手と手を繋いで歩くと、いつしか私の体温なのかあなたの体温なのか分からなくなってきて、だけど、真っ白い靄を抜けた時にあなたのあの表情を見ることができたのなら、私はもう満足なんだと思って、私はまた再びあの真っ白い靄の中へと誰かを助けにいくのかもしれません。
そして、そうやって何度も何度も何も見えない真っ白い靄の中に入っては、誰かの手を掴んで靄の外へ連れ出して、を繰り返していくうちに、やがて靄は晴れていって、私も誰も迷わなくなるので、今はあの舞台の上で大きな声でまっすぐと台詞を言っていたあの男の子のように、誰かを前にしても自分の台詞をスラスラハキハキと言えるようになっていることもあるでしょう。
やがて、私は舞台の上の男の子が「自分だったんだ!」と気づいて、舞台の下から見ていた男の子は小さな頃の憧れを持っていた自分だったと知って、そうすると昔の小さな男の子に今の立派な自分を見せたくなったので、私はしっかりとまっすぐ視線を前に固定したまま、あの台詞を堂々と大きな声で、体育館中に轟かせるのです。
ひとつ、爽やかな空気が頭に流れていきます。
ふたつ、身体がだんだんと軽くなっていきます。
みっつ、大きく深呼吸をして頭がすっきりと目覚めます。




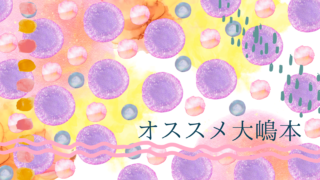






コメント