今回も引き続き、【それ、あなたのトラウマちゃんのせいかも?】を再読した気づきを書き連ねていきます。
読むたびに新しい発見があるので、何度読んでも新鮮です。
心の傷があると、そこから起こる不具合を自覚できないことが多いです。
なので、何回トラウマちゃんの本を読んでも、記憶から抜けてしまうのかもしれません。
FAP療法で心の傷を治療していくと記憶がきちんと整理されて、「こんなことあったな~」と自覚できるようになるのかもしれません。
【汚い話注意】真っ白だった母親のトラウマ
初回面接で母親の性格特徴を聞き取った時の印象は真っ白だったのに、その母親が「鬼の形相で男の子を殴っていた」という記憶が抑圧されていた“怒り”に注目を向けた時に出てきた。(p106)
私もFAP療法での初回面接の時は、母親のイメージは「真っ白」でした。
かなり後になってから、「私の中の母親のイメージって真っ白だったんだ!」と気づきました。
FAP療法を受けて6回目ぐらいの頃、私は急に婚活を始めました。
この頃は鬱で実家に戻ってきていたのですが、祖母の認知症が進行してきて、夜間徘徊のようなものをするようになっていたんです。
祖母は、毎晩1時間ごとに起きてトイレに行っていたらしく、祖母が階下で電気をつける気配がした瞬間に父親が怒鳴りながら階段を下りていくので、私は当時ようやく貯金ができるほど稼げるようになっていたのに毎日寝不足で思うようにパフォーマンスができず苦しんでいました。
祖母が通っていた施設の職員さんには、虐待を疑われていたりもしたそうです。
あれが虐待ならば、私は幼少期から同居していた祖父と父親に同じようなことをされてたんだけどなあと思っていました。
そんなことがあって、実家を出て再び一人暮しをしたいと真剣に考え始めていたのですが、どうしても気がかりなことがあったんです。
前回、大阪で一人暮ししていた時、実はまったく掃除してませんでした。
驚くことに、7年間一切掃除しなかったんです。
高校生の頃から足の踏み場がない汚部屋に住んでいた私がいきなり掃除や片付けができるはずなく、さらに風呂掃除なんかどうやってすれば良いか分からなかったので、自分では一切できませんでした。
同棲していた彼氏たちがちょくちょく掃除をしてくれていたりもしたのですが、退去する1年前からは本当の意味での“一人暮し”になっていたので、誰も家に来ることがなく、汚い床も見慣れたものになっていました。
そんな私でしたが、実家に帰ってきてFAP療法を受け始めてから勉強机や日記、読まない本をすべて捨て始めたりして、部屋をきれいに片づけられるようになっていたのですが、どうしても「汚いもの」を見たくない!
たとえば、風呂場の排水口に溜まった髪の毛とか、床に落ちている自分の髪の毛とか、まあ主に自分の髪の毛だったと思います。
(もうこの感覚を忘れてしまったので、曖昧です(笑))
私はFAP療法を受ける前に毎回、今の自分の悩みをすべて書き出します。
そして、中指ビンゴで一個ずつ「この悩みを今日のカウンセリングで相談する?」と手を振って決めていました。
それで、6回目にようやく「引っ越ししたいけど、汚いのが嫌で掃除できなくなるのが心配」ということを相談してみました。
当時の記憶が曖昧なのですが、この時カウンセラーの先生と一緒に「心に聞く」をやりました。
何を聞いたのかは忘れました。
すると、母親が私を掃除機で殴るイメージが出てきたんです!
え!と思って、ビックリしました。
なんで殴られてるの!と、心の中で衝撃を受けました。
さらに心に聞いていった時に、ある数字の羅列が脳内に浮かんできました。
それはデジタル時計のようなイメージだったのですが、私には何の数字なのか分からず、カウンセラーの先生も「なんだろう?」と言っていて、しばし2人で悩みました。
「うーん…」としばらく考えていると、突然ひらめいたんです。
私の脳内に浮かんできた数字は、大阪の家を退去した日付だった!
そして、母親に掃除機で殴られているイメージは「もしかして、私が掃除できないことを怒られている?」と思いました。
しかし、私が母親に怒られているのではなくて、私が掃除ができなかったのは「母親が邪魔してきたから」ということを心は伝えたかったみたいなんです。
幼い頃から私の中の母親のイメージは、「きれい好きで、すぐ物を捨てる」人でした。
反対に私は掃除も片づけもできなくて、部屋の中は泥棒がひっくり返したみたいな惨状で、物をどんどん溜め込んでいくタイプ。
そんな自分を母と比較して、いつも「なんで片づけられないんだろう」と責めていました。
だけど心がいうには、母親が私を「片づけられない子」にして、母親が自分自身を傷つけていたんです。
ちなみに、このカウンセリング後に引っ越ししてからも、しばらくは「落ちた髪の毛が気持ち悪い!」問題で苦しみました。
その頃は必ず夜にお風呂に入らないと「寝れない!」と強迫的になっていて、でも排水口を見るのが嫌すぎて、どんどんお風呂に入る時間が遅くなっていってしまう。
お風呂に入ったら入ったらで「汚いものを見てしまった…」と瞼の裏にこびりついて目を瞑れないから、いつまで経っても眠れない。
そして、窓の外が明るくなってきて鳥の鳴き声が聞こえてくる…。
もう本当にこれが嫌で、何度も何度もセルフFAPしました。
何度もやってるのに根底のトラウマが取れていないのか、全然髪の毛のことが解決しない!と思って怒りながら、ある日「心よ!髪の毛が気持ち悪いのはなんで!」と聞いてみました。
すると心は「それは母親の感覚!」と言ってきます。
え?と思って、「心よ!母親はなぜ髪の毛が気持ち悪いと思ってるの?」と聞いてみると、小学生の時に私が宿題をしながら髪の毛を抜いていて、気づくとグレーの絨毯一面にびっしりと落ちていた髪の毛を見た時の真っ青になった母親のイメージが頭の中に浮かんできました。
(小学生の私は浅はかで、絨毯がグレーなので落ちた髪の毛が見えないと思っていました。否認です。)
「私のせいなんかい!」と思いながらさらに潜っていくと、母親は私が髪の毛を大量に抜くのは「自分のせい」だと思っていたみたいだということに気づきました。
それと同時に、リフォーム前の実家の風呂場が浮かんできたんです。
母親は毎日「汚い!」と言いながら風呂場を掃除していました。
母親は汚いのが大嫌いで掃除好きなのに、私はなぜか気管支炎みたいなものになって医者に「お母さん、ちゃんと部屋の掃除してください!」と言われる。
(母方家系は呼吸器系が弱いので掃除していたのもあったと思います。そして、この時の私の謎の気管支炎は今になって思えば過呼吸発作でした)
母親は汚いものが大嫌いで汚いものを見ると激怒するのに、私は小学校高学年になってもトイレを我慢する癖があって漏らしてしまうし、風呂場でも漏らしてしまう。
(肛門期がダウト~!です)
ちなみに母親がはじめてこの家に来た時はまだ土間があって、家に入るとサーッと虫やゴキブリが一斉に逃げていっていたらしいです…ぞわぞわ。
妹は私とは違って汚物的な問題はないのに、いつも私は「汚い」で母親の精神を参らせてしまっていました。
でも、これって母親の心の傷だったんだなって、気づいたんです。
私が大人になってから自分の抜けた髪の毛に憎悪するのも、汚いものを触りたくなくて潔癖症になっていたのも、すべて母親のトラウマを私が背負っていたから。
それからは、お風呂に入って排水口を掃除するたびに「髪の毛が嫌いなのは母親」と思い出していました。
すると、なんだか案外平気なんですよね。
今では落ちた髪の毛に憎悪するほどの激しい感覚がなくなってしまったので忘れてしましましたが、FAP療法で記憶を整理していくと、真っ白の母親のイメージからいろいろ出てきたなあと懐かしく思います。
瞑想ってなんでみんなできるの?
メンタリストDaiGoさんの配信を見て、「瞑想」にチャレンジしようと頑張っていた時期があります。
瞑想することで得られるメリットはたくさんあります。
日常的に短時間でも瞑想の時間を持つことで、メンタルが安定したり、睡眠の質が上がったり、収入が上がったり…。
そんな恩恵にあずかりたくて、毎日瞑想していたのですが…全然集中できない!
まあ、集中力を上げるために瞑想をしたりするものなんですが、とにかく雑念が多すぎる。ずっと目を閉じていられない。
いろんな瞑想の種類がありますが、私は「思考がそれたら戻すだけ」の瞑想をしていたので、余計な思考が湧いてきたらそれに気づいて「無」に戻したり、「あ~今余計なこと考えてるな~」と思考を実況中継していたりしていましたが、まっっったく瞑想の効果が分かりませんでした。
その内に時間のムダだと思って、瞑想をやめました。
ちなみに、1年ぐらい頑張ってました。瞑想のためにアップルウォッチ買ったし。
後から知ったのですが、トラウマが深いと瞑想が逆効果になる場合があるそうです。
鈴木祐さんの【無(最高の状態)】に書かれています。
そりゃ我々トラウマ持ちは、安静時にフラッシュバックして恐怖を回避しようとするシステムが自動的に作動してしまうので、瞑想で凪を目指せば目指すほど、回避するための不快な記憶が湧いてきて落ち着かないわけです。
実は大嶋先生の【トラウマちゃん】の本にも、ちゃんと書いてあったんです。
何回も読んでいるのに、記憶に残っていなくてガーン!です…。
大嶋先生は、瞑想も恐怖に浸る方法の1つであると仰っています。
根底の恐怖は回避すると増幅するので、瞑想することによって回避せず“恐怖に浸る”と、人間の恒常性が働いて脳の過活動が収まっていくはず。
しかし、瞑想を恐怖に浸ることではなく、根底の恐怖に向き合わずに回避することに使ってしまうと、脳の中の凪は収まるどころか激しい嵐になっていく。
トラウマの人が瞑想中に目を閉じると襲ってくる不快な記憶たちは、マーラに作られた“恐怖”と同じであると大嶋先生は仰る。
シッダールタは、このマーラが作った幻想の恐怖と向き合って悟りを開いたのです。
瞑想をやっているときは“恐怖”を回避できるけど、普段の生活の中では“恐怖”を回避した分、増幅して「脳の過活動が収まらない」ということになってしまうこともある。(p155)
気をつけないといけないのは、「じゃあ、向き合って乗り越えてやるぜ!」と“行動に移そう”とする時。
一見「行動すると“恐怖”を回避できる」という感覚になるが、行動すること自体が回避行動になってしまう場合もある。
私の場合だと、「働かずにお金がなくなるのが怖いから、じゃあ働きまくろう!」としていたこと。
恐怖を乗り越えようと行動しているように見えて、根底の恐怖を見るのが怖いから闇雲に動いて“恐怖”を回避していたのだと思います。
その証拠に、何度も体調を壊したり燃え尽きたりして、まったく動けなくなる時期が定期的にくる。
動けないと「このままだとお金がなくなる!」という恐怖がどんどん増幅していってしまう。
オーバーワーク癖はフラッシュバックを止めるため
普通の人は、何もない安静時にきちんとリラックスすることができる。
でもトラウマの人は、安静時に解離した“恐怖”がフラッシュバックして襲ってくるから、心が休まらない。
休まりたいと思っているんだけれど、完全にリラックスしてしまうとドーン!と恐怖が自分に襲い掛かってきそうで怖いから、おちおち気を緩めることができない。
これを私のイメージで言うと、ぼんやり信号待ちしている時に暴走したトラックが自分に突っ込んでくるような感覚です。
もしくは、ぼーっと自然体で立っていると突然後ろから鈍器で殴られるような、突然背後から首にロープをかけられるような、そんな感覚である。
だから気を抜いたりしたら、抜いた隙間から嫌な出来事が突っ込んでくる!というのが怖くて、何も起こってないのにずっと緊張状態を拭えませんでした。
これを当時の意識にすると、たとえば個人事業主を始めたばかりの頃。
休めばそれだけ売上は減る。
休憩に行ってる間に、もしかしたらお客様を逃しているかもしれない。
私が休んでいる間に、お客様が他の人のところに流れてしまうかもしれない。
そんな恐怖があったから、休むに休めなかった。
休みの日でも毎朝9時に電話鑑定をストップしないと、予約が連なってしまう。
たぶん他の人からしたら、「予定があって鑑定できないなら、そのままスルーでいいやん」という。そういうルールだし、お客様も理解されているはず。
だけど、「断ってもいい」と言われても、私にはそれが恐怖でできなかった。
収入がなくなるというのが意識での恐怖だったけれど、きっとその根底にあったのは「お客様が離れていってしまう」死の恐怖。
こうやって、休みの日でもずーっと仕事のことばかり考えていて辛いので、2週間休まないとか普通だったし、自分ではどことなく「休まず働く自分」が誇らしかった。
でも、これって今思えば、根底の恐怖から回避していたのだと思います。
では、根底の恐怖はなんだろう?と考えてみる。
ただ、お金がなくなる、稼げなくなるのが怖くて休めなかっただけではない。
休日に1人、家でぼーっとしていると職場であった嫌なことを思い出して「あ゛ー!!」ってなって苦しいので、休むのが怖かったのもある。
けれど、休まないと身体が持たないのもなんとなく分かっているから休むのだけれど、休みの日は何かと用事を作ってほとんど家でゆっくりできる日はありませんでした。
今にして思えば、安静時のフラッシュバックを止めたくて休むのが怖かったんだなあと思いますし、バリバリ根底の恐怖を回避していたように見えるのですが、当時の自分は「働かなきゃ、お金がなくなる!」と信じてどんどん休みを減らしていました。
家に1人でいると、ムカつく人の言動がひっきりなしに思い浮かんでくるし、逆に自分のあの言動はダメだったかもしれないと後悔や反省も止まらなくなってしまう。
それが怖いから、その怒りや反省や後悔を払拭しようと、休みなく職場に出かけていく。
何もしないと不安と怒りに押し潰されそうになってしまうから。
「大丈夫だ」という安心がほしくて、休まずに働く。
でも、休んでいないから心身ともにボロボロで、満足なパフォーマンスができないことに苦しむ。
そして、仕事から帰ってきたら、怒りや反省や後悔にまみれて、休むとどんどんお客様が離れていってしまうような気がするから休めなくなって…を繰り返していました。
「何か不安なことを作り出してインターネットで情報検索をし続けて、それが止められなくなってしまう」というのも、トラウマで解離した“恐怖”が元になっていて“不安”はその“恐怖”からの“回避の道具”に過ぎなかったりする。(p121)
“不安”も回避の道具であるなら、「お客様が離れていってしまう不安(恐怖)」の下にはどんな根底の恐怖が隠れているのか?
まず、お客様が離れていくということから連想される「収入がなくなる恐怖」に浸ってみる。
すると、胸のあたりがざわざわするので、ダミーの恐怖だと分かる。
さらに「収入がなくなる恐怖」に浸って根底の恐怖を探ってみると、今度は息ができなくなってきて「みんなと同じになれない恐怖」が浮かんできた。
収入がなくなることで、友だちや周囲の人と同じように生活を楽しむことができなくなって、孤立してしまう恐怖だろうか?
それとも、同年代の世間一般並に稼げなかった劣等感だろうか?
もしくは、他の占い師のように、お客様に接することができない恐怖だろうか?
さらに「みんなと同じになれない恐怖」に浸ってみると、水中で息ができなくて頭が破裂しそうになるあの感覚になる。
というとこは、これもダミーの恐怖である。
「みんなと同じになれない恐怖」を感じながら、もっともっと潜ってみる。
すると今度は、保育園の時の自分が浮かんできて「もっと頑張らなきゃ追いつけない!」という焦りが出てくる。
この映像はなんだろう?と思いながら眺めていると、「嘘がバレる恐怖」が出てきた。
自分が人よりも劣っていることを見破られたくなくて高下駄を履いているんだけれど、いつボロが出て「嘘吐き!」とみんなに罵られるのだろう…と、内心ずっとヒヤヒヤしているあの感覚。
顔は笑っているけれど自分の内面は冷え切っていて、嫌な汗が肌の上を滑っていく。
「嘘がバレる恐怖」を頭の中で何度か唱えてみると、息がしやすくなってきた。
あれ?「収入がなくなる恐怖」って、「嘘がバレる恐怖」なの?と半信半疑だったので、もう一度「お客様がこのまま離れていなくなって大変な目に遭う!」という自分を想像してみようとする。
だけど、さっきまであった「お金がない!」という焦燥感をまったく思い出すことができなくなっていたんです。
なぜ、私が「このままではいずれはお客様がみんな離れてしまって無一文になって途方に暮れる!」と怯えていたのかというと、きっとお客様の前に出しているのは“偽の自分”だと思っていたからでしょう。
だから、本当の私を知ったらみんな離れていってしまうと思っていたのが、「お金(収入)がなくなる!」という焦りに変換されて、自分は嘘なんか一切吐いてません!と根底の恐怖を回避していたようなのです。
嘘をつくことって、案外大事ですよね。
大嶋先生の【それでも大丈夫】では、嘘を吐くことは人前に出る時の「身だしなみ」と同じと書いてくださっていました。
川上弘美さんは【蛇を踏む】のあとがきで「うそばなし」の話をされています。
幼少期から自分を守るために嘘ばかりついていて、毎日断罪されるような気持ちで生きてきた私は、大嶋メソッドと出会ってからは「正直に生きる!」をモットーに占い師をしていました。
でも、よくよく考えてみたら、自分を守るためにやっぱり嘘が必要な時もあるし、たしかにプライベートと仕事の時は若干キャラが変わっているかもしれないけれど、どちらかが本物でどちらかが偽物というわけではない。
どっちも本当の私だ。そして、真実なんかは時の流れとともに変わっていく。
嘘を吐いたら閻魔様に舌を切られる!と怯えていた子どもの頃を思い出しました。
👇こちらが私が過去に書いた【それでも大丈夫】のレビューです

今から仕事なのに力が出ない!
朝起きて、用意をしないといけないのに起き上がれない。
「やらなきゃ」と焦っているのに、やる気がまったく出ない。
これから気合入れて仕事する時間なのに、なんか怠いし力が入らない。
長年、私はこの症状に悩まされてきました。
身体のどこかが病気なのかと思って、甲状腺の検査を受けに行ったりもしたのですが、どの病院で何を検査しても健康な人よりも健康と言われる。
トラウマの人の脳の反応は普通の人と逆である。安静時に緊張が高くて、ストレス刺激が加わったら、頭が真っ白になって動けなくなり何も考えられなくなってしまう。(p125)
トラウマの人の脳は、普通の人の脳と反応が逆になるので、ここぞという時にへなへな~と力が抜けてしまう。
普通の人が適度なストレス刺激で「やったるで!」と気合を入れられるのに対して、トラウマ脳の人はストレス刺激で緊張が下がるから、「緊張感出して頑張らなきゃ!」という時に逆に力が抜けてしまう。
(ストレス刺激が麻薬のようになっていて、無理やりリラックスをさせるために注入されているようなものだからです)
これが分かっているようで分かっていなかったので、「なんでやる気が出ないんだろう?こんなに頑張ろうとしているのに!」とあらゆることを試してみた。
食事が悪いんだとか睡眠の質だとか、体力だとか、自分の怠け癖がいけないんだとか。
ある程度どれも一応効果はあったのですが、でもなぜかどうしても力が入らない時がある。
「肝心な場面で力が抜ける」というこの症状は、実はトラウマ反応だということに気づくのはかなり経ってからでした。
ちなみに、トラウマの恐怖っていうのは「命の危機」が目の前に迫っていて、今まさに「死ぬ!」「殺される!」という状態です。
過去のトラウマ体験で感情記憶が解離してしまっている人は、目の前で起こっていることに当時のトラウマの“恐怖”を結び付けてしまうから、なんでもないことに対して「命の危険が迫ってる!」と感じてしまう。
だから、突然イライラしたり、理由も分からず不安になったりする。
じゃあ、「今、目の前で起こっていないって分かればいいんでしょ?」というと、そういうことでもない。
この理論を分かっていても、分からないんですもん!
今感じているのが、ダミーの恐怖だっていうことが。
私の場合、仕事の大事な場面でやる気が出ない→ベストパフォーマンスを出せないとお客様を満足させられない→お客様に嫌われる→お客様が離れていく→売上がなくなる→お金がなくなる→生きてられない…みたいな構図が頭の中に浮かんでいました。
もし、トラウマ脳でない普通の人だったら不安を適度な緊張感に変えて、「このままではいけないから、力を入れないと!」と力を発揮することができます。
しかし、トラウマの人は状況にそぐわない過剰な恐怖を感じて、パニックになったりする。
これが「死の恐怖」を感じている状態である。
朝、起きてさっさと用意をしないと仕事に遅刻してしまう。
遅刻すると、お客様を逃してしまうかもしれない、怒られるかもしれない、見放されるかもしれない…いろんな最悪な状況を想像するけれど、自分の中の焦りとは反対に体にちっとも力が入らない。
普通の人だったら、ストレス刺激が入ったら「気を付けよう!」と脳内のグルコースがアップして集中が増すから、丁寧に包丁を扱うことが出来る。(p133)
しかし、トラウマの人は最悪な状況やストレスフルな状況を脳内でイメージしてしまって、それがストレス刺激となるから脳内でグルコースが低下して、注意散漫になったり手に力が入らなくなります。
もしくは、私のようにさっき食べたばかりなのに急激に空腹感に襲われて、バクバクとお菓子やジュースを食べてしまったりする。
すると、想像した通りの最悪の結果が起こってしまう。
そして「ほら!私の思ってた通りになったでしょ!」と、さらに幻想の世界へ逃げなければならなくなる。
他人からしたら「そんなわけないんじゃん!」って見える。
でも、私からしたら自分の目の前には悪夢が広がっていて、誰かに悩みを理解してほしいけれど「こんなことを言ってもまたバカにされるだけかもしれない」と思って、1人怒りを抱えたまま苦しみ続ける。
じゃあ、どうするのかというと、『根底の恐怖』を探りましょう!というのがトラウマちゃんの本のテーマである。
「自分の根底にはどんな幻想の恐怖がある?」と探ってみる。
朝起きて準備しないといけないのに起き上がれない時、「仕事ができないやつだと思われてしまう!」という不安を感じています。
それは「見捨てられる恐怖かも?」と思って、この恐怖に浸ってみます。
けれど胸のあたりがざわざわするので、これはダミーの恐怖ということになります。
「見捨てられる恐怖」にさらに浸ってみると、職場で誰も仲間がいなくて無視されて困っている自分の姿が見えてきました。
「これは孤立する恐怖かな?」と思って、この恐怖を感じてみる。
ゆっくり、ゆっくり「孤立する恐怖~」と頭の中で唱えてみる。
すると、今度は喉が締まる感じがして、息苦しくなりました。
ということは「孤立する恐怖」もダミーとなります。
さらに「孤立する恐怖」に浸っていくと、今度は実家のリビングが見えてきました。
ある晴れた日に、大きな窓からおだやかなやわらかい陽射しが差し込んでいる。
これは高校1年生の春休みの光景です。
ファッションに興味を持って、はじめてファッション雑誌を買って読み耽っていたあのなんでもない日常の一片。
この情景を眺めていると、なんだか涙が出てきそうになったのですが「根底の恐怖は何だろう?」と思って恐怖(悲しみ)に浸ってみると、「おだやかに過ごす恐怖」というのが出てきた。
このままではちょっと長いので、もう少し言いやすい言葉に言い換えられないかなあと考えてみる。
そう、私は本当は晴れた午後の昼下がりにぼんやりとひなたぼっこをしていたいんだけれど、それをすることがいけないような気がして、いつも罪悪感や焦燥感が湧いてくる。
なぜ?と思いながらこの感覚に浸っていると、「ひとりぼっちになる恐怖」と言葉が頭の中でリフレインする。
「え?孤立する恐怖と一緒じゃないの?」と思うのだけれど、そうではないみたいです。
「ひとりぼっちになる恐怖」というのは、ミラーニューロンで他人の不快感を共有することで「繋がっている」と安心できるような状態(他人の不快感を自分のものにして安心している)からきているようなのです。
つまり、「おだやかに過ごす」というのは脳の過覚醒が収まって凪になっている状態なのだけれど、そうなってしまうと他人から「薄情なやつ!」とか「あなただけずるい!」と非難されそうな気がするから、みんなと同じように不快まみれでないと安心できない恐怖ということになります。
「ひとりぼっちになる恐怖」をゆっくり唱えていると、高校1年生の春休みに感じていたあのおだやかな春の陽射しの風景が、だんだんと薄く色褪せていきました。
もしかしたら、「おだやか」という基準さえいらないのかもしれません。
そんなことを感じていると、「朝、仕事に行く準備をしようとすると力が入らない」という症状は、「サクサク用意しちゃったら、ダメ!もっと仕事に行くことを嫌がらないと!」という自分の中のリミッターになっていることに気づきました。
大嶋先生の【ちいさなことで感情をゆさぶられるあなたへ】に出てきた「みんなと同じになりたいの?」という呪文を思い出します。
みんなと同じように不快感を感じていなくても大丈夫なんですよね。
昔から「のんびりや」と言われていた私は、「人と違う」ということにトラウマを持っていたのかもしれません。
みんなが嫌だと思っていても、本当は私は何とも思ってなくても大丈夫。
母親が父親のことで怒ったり悲しんだりしていても、私は自分のことを楽しんでいても大丈夫。
背負う必要はないということなのでしょう。
「他人と自分は違う」という感覚は、いつしか私の中で劣等感となって「みんなみたいに愛されない」とか「普通にしていたら嫌われる」と思ってしまっていました。
そして、それは自然なことで、だから「失敗して嫌われてしまう!」という状況や予定がある日に私は目が覚めても力が入らず、布団から起き上がれなくなっていたんです。
そして失敗を繰り返し、「愛されない自分」という最悪の結果を無自覚に作り上げていたのかもしれません。
親の「心配」の背後に回避している恐怖があるのかも
大嶋メソッドでは、“心配”はダブルバインドだと他の本にも書かれていますよね。
【トラウマちゃん】の本の中では、親が根底の恐怖を回避している時に子どもを心配するといったことが書かれています。
でも、親が自分の“恐怖”を回避するために子どもの心配をし続けるということは、ある意味で子どもを利用していることになり、そこでの“心配”の背後に親の回避をしている恐怖が隠されている。(P148)
親が「死の恐怖」を今まさに感じていると、当然親は“恐怖の回避”をしようとする。
そして、“恐怖の回避”をするために子どもを心配する。
ということは、子どもに心配するところがなくなってしまうと(親の心配を奪ってしまうと)、親は「死の恐怖」を回避できなくなって、直視しないといけなくなる。
だから、親がいつまでも“心配”できるような「ダメな子」を演じたりしてしまったりする。
そんな子どもは「親の思う通りの人生」を生きることになるので、親の感覚で生きているということになってしまう。
そして、そこには「自分の選択に親の生死が掛かっている」というプレッシャーが常につきまとっているのです。
「自分の選択で親の生死が掛かっている!」という感覚まで、自覚できないかもしれません。
少なくとも、私はできませんでした。
けれど以前、心に聞いた時に同じような答を返されたことがあります。
何を質問したのか忘れましたが、心に「あなたの失敗は母親の失敗」であるから、それが気になるといったことを言われたことがあります。
世間の評判だったか、自分の不快感だったか、自分の運の悪さだったか、そんな感じのことを心に聞いたのだと思います。
私はネット上で口コミや評判を書いていただくような仕事をしているので、そこで私の悪事(実際、悪事を働いていなかったとしても)を誰かに暴露されたら…と毎日気が気ではなかった時期があります。
だから、常に清廉潔白でいないといけない!という恐怖が私の中であって、いつかユーチューバーの炎上みたいに知ってる人にも知らない人にも非難されるようなことになったらどうしよう…と心底苦しんでいました。何も起きていないのに。
そんな時に心に聞いて、「ああ、そうか。私が世間のみんなから非難されたら、母親が非難されることと同じことなのか」と腑に落ちたんです。
母親の「正しい/間違っている」の基準で考えていたから、世間の目がものすごく怖かったのです。
でも、私が「世間に受け入れられない行動をしたら、死ぬ!」と思っていた恐怖は、母親が「根底の恐怖」を回避していたから感じていた恐怖なのかもしれません。
では、母親の根底の恐怖とは何なのか?
私にとって母親は支配者であり、支配者は「支配すること」がお仕事なので感情などないかもしれませんが、もし母親が「あなたが世間の人に傷つけられたら…」と私のことを心配していると仮定したら?
ある光景が浮かんできます。
私が小学校2年生になった頃だったか、クラスの男子全員が私に謝りに家に来たことがあります。
たしか私が「学校に行きたくない」と母親に言ったから、母親が担任の先生に相談したのだと思います。
私は母親に「男子に虐められているから学校に行きたくない」と言ったのですが、私はそれを「大げさに言ってしまった、どうしよう…」とずっと悩んでいました。
当時の私の感覚では、男子に苦痛を感じるほど何かされた感覚はなかったのですが、男子1人1人何をされて嫌だったのかを言ったような気がします。
ミュンヒハウゼン的な行動だったなあと当時から感じていたので、長年この時の自分の行動を「なんであんな大嘘吐いたんだ!」と恥じていました。
男子全員1人ずつ、ベッドに寝ている私に謝ってきます。
心の中では「あなたたちを悪者にしてごめんなさい」とずっと思っていました。
しかし今の私が思うに、この時の「男子が私を虐めていた」という感覚は多分正しかったと思うし、それは小学校1年生の時の担任のいじめから派生したものではないのか?とも思うのです。
けれど、母親の“心配”がそこにあって、根底の恐怖を回避するために私を使ったのだとしたら、ここには何が隠れている?
たぶん、母親が「仲間外れ」になりたくなかったんだと思います。
母親は、京都から奈良に来て親しい友達が誰もいなくなってしまって、他人との関わりも苦手。
いつも表面は笑顔で接しているけれど、できれば人と関わりたくないと思っている。
代理ミュンヒハウゼンじゃないけれど、昔から体が弱かった母親と同じく私もずっと体が弱かった。
でも、私はとくにどこが悪いとかがなかったんですよね。
母親は私を“心配”することによって、誰も知っている人のいない土地で生きていこうと頑張っていたのかもしれません。
私が家族のスケープゴートとなって「困った子」となることで、母親のことを誰かが心配してくれる。
まあ、“心配”で繋がっているから、どちらも“心配”を回避してることになるやん!とも思うのですが、そうやって人と人との関係って繋がっていくってところがありますもんね。
だから私は母親が苦痛で「ギャー!ギャー!ギャー!」と叫ぶたびに、一生懸命母親の苦しみを止めようとしてきた人生だったのかもしれない。
今でも母親は“心配”することでコミュニケーションを取ろうとしてきます。
昔の私も、他人を“心配”することで仲良くなれると思っていました。
そんなことしなくても、仲間外れなんかにならないのに…と今なら知っています。
母親に心配されなくなっても、母親がひとりぼっちになって苦しみながら死ぬことはないと、もう今の私はちゃんと分かっているんですよね。
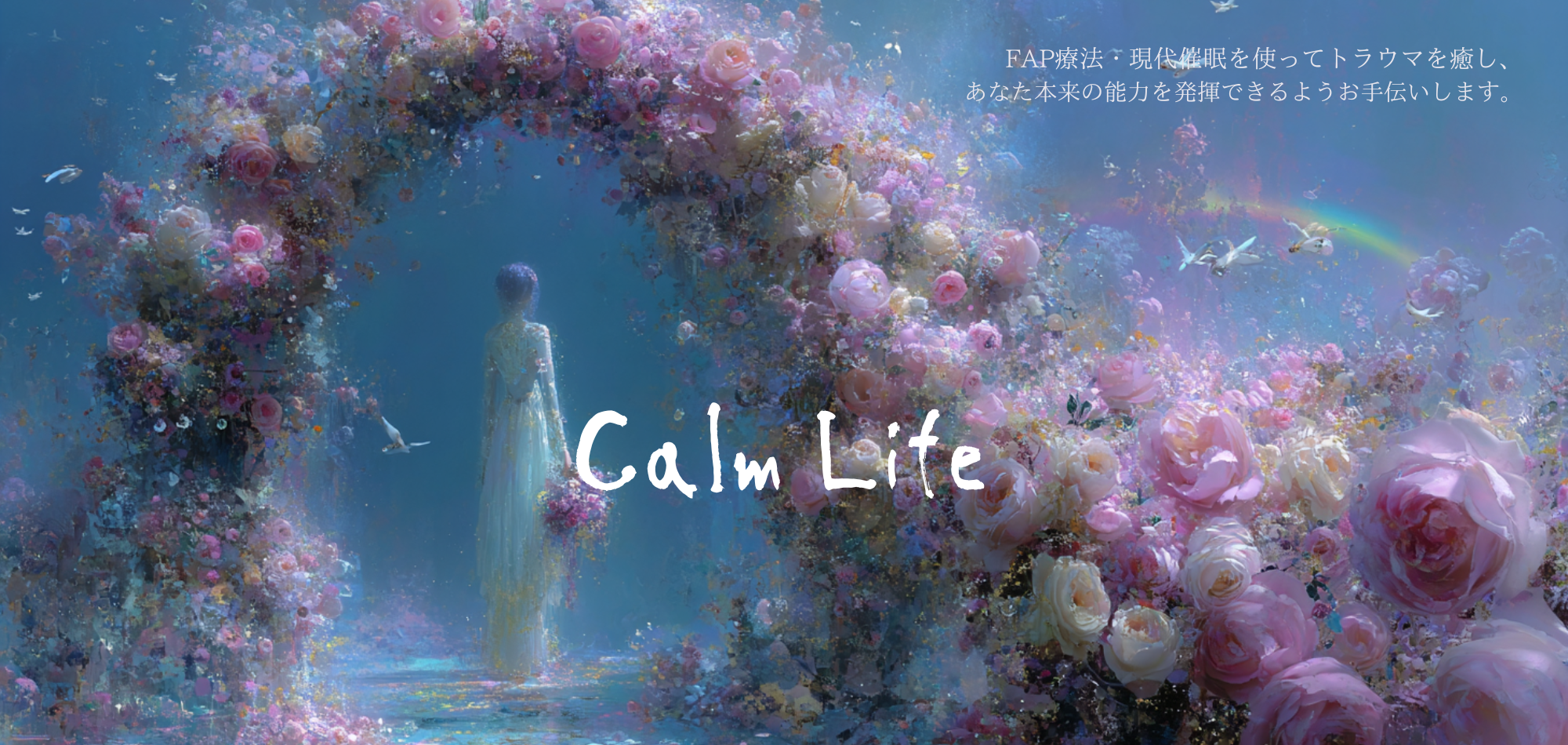





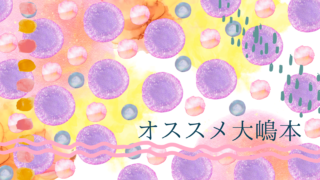







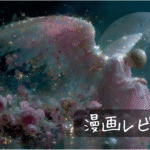
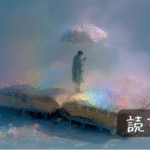
コメント