悩んでいる時、ひとりぼっちでさびしい思いをしている時、心にじんわりとあたたかい光を灯してくれるような本―――それが【水中の哲学者たち】
夢中になって読みました。
人間関係がうまくいかずに孤独感を感じている人。
「自分なんかもうどうでもいいや」と投げやりになっている人。
どうせ一生孤独で誰とも分かり合えないんだ、と思っている人。
仕事でしんどい思いをしている人。
悩んでいる人全員に、とにかく読んでほしい!
作者の永井玲衣さんは、各地で「哲学対話」を行っている哲学者です。
「話す」よりも「きく」ことに集中してみる、とは永井さんが仰る「哲学対話」のルールの1つ。
私はこの言葉に、すごく救われました。
哲学対話の場では、発言せず「きく」だけでも大丈夫なんです。
それが私にとっては目からウロコでした。
小学校の高学年の時に、机を円形に並べて行ったディベートが苦痛で仕方ありませんでした。
何か言わないと仲間外れになる!とおどおどしていました。
多くの人でなくても自分以外の誰かがそこにいて私に何か語ってくれているのなら、自分も何か言葉にして答えないと!と焦ります。
誰かの話を聞いているのに、何も反応しない(ただ聞いているだけ)なのはいけない!となんとなく思っていて、だから一生懸命相手の言葉を受けて何かしらを喋ろうとしていました。
けれど、そうすることが自分にとってはとてもプレッシャーだったんです。
でも、「きく」だけでいい。
「きく」だけでも哲学対話に参加しているんだ!と。
これが自分の求めている「安心できる場」なのだと知りました。
私は小学生の頃から手を挙げて発表するのが苦手で、大人になってからも人前で何か話すとなるとあわあわとどもってしまっていました。
「挙手」するとか「意見を言う」場となると、ものすごく緊張して喉が詰まってしまいます。
だけど、「きく」だけでいいって知った時、頭の中が静かになって、すんなりと相手の言葉がすべて入ってきたんです。
それまでは「ああ言おう、こう言おう」とあれこれ頭の中で考えてしまっていて、たぶん相手の言葉の何割かを聞き逃していたと思います。
自分のことしか考えていなかったんですよね。
でも、「きく」ことに集中したとき、そこに言葉は必要なかったんだって気づいたんです。
読む前の自分・今の自分の状況
「きく」だけでよい場って、とても居心地がよい。
これこそが求めていた安心感だと感じたこともすごく大きな発見だったのですが、もう1つ大きな変化があります。
「悩むということは“問い”の始まり」であるということです。
私は元々哲学に興味があって、高校の時の倫理の教科書や公務員試験の予備校に行っていた時の哲学者のページなどは今でも大切に保管してあります。
ずっとずっと「読まねば!」と思いながら、心理学書ばかり読んできていました。
そんな時に永井さんの本と出会って、「哲学って“問い”なの!?」と知ったんです。
“哲学”というと難しい専門用語がたくさん出てきて、答の出ないことについて延々と悩み続けることだと思っていました。
だから、哲学者のみなさまには本当に申し訳ないのですが…「悩むよりも解決優先だ!」と思って簡単な答がすぐ手に入るビジネス書ばかりを読んできたのです。
さらに、哲学者の人って異様に頭が良くって、その哲学者たちの言葉を理解できない自分自身に絶望してしまうのも怖いと感じていました。
でも、そうじゃなかったんです。
永井さんは高校生の頃、お風呂に入っている時に突然「なんだこれは?」と世界の奇妙さに気づき、哲学書を手に取った。
しかし、そこに書かれていたのは
存在とはばばばばばびぶぶべべぼ、あるところのものびびびばば、ではないところばばっええじゃややえあうくしたわかちこわかちこ。(略)
本を閉じた。脳が爆発してしまう、と思った。(p016-017)
である(笑)
これはこの本の一番最初のお話なんだけれど、読んだ時に「なんだ、わからなくていいのか!」と安堵しました。
それから、ぐんぐん永井さんの世界に引き込まれていったんです。
私にとって「わからない」とはとても怖いものでした。
教室の中で自分1人だけがこの答をわかっていなかったら、どうしよう…
未来がわからないから、動けない…
相手に好かれているか嫌われているかわからないから、話しかけられない…
いつも何か「絶対的なもの」がないと、不安で不安で仕方ありませんでした。
そして、誰かの悩みには的確に答えを出さないと!とも思っていました。
けれど、この本を読んでから、私が答を出すのではなく「一緒に悩む」を大切にしたいと思うようになったんです。
タイトルの【水中の哲学者たち】というのは、答の出ないわからない“問い”に立ち向かう時に感じる孤独の中、“問い”に深く深く潜っていく様子を表現されたものです。
たしかに、深く考えることは、水中に潜って息を止めて集中するあの感覚に似ているかもしれません。
しかし、私は「なるべく悩みたくない」と“問い”を嫌って生きていたので、水中の中ではいつもむやみにもがいて溺れかけていました。
考えるということは、むしろ弱くなることだ。(p121)
とても刺さりました。
誰かを知れば知るほど「自分が今まで信じてきたものは幻だったのか?」とぐらっと揺れたり、自分がどれだけ傲慢だったかを思い知らされたりします。
「対話」というのは、あなたが私と同じ人間だということを思い出させてくれます。
すると、私は今まで自分が見てきた世界や信じてきたことが誰かを傷つけていないか?私が当然だと思っていたことが“あなた”にとっては違ったのか?じゃあ、何が「最適解」なのか?と世界がぐにゃぐにゃと原型を歪めていきます。
途端に、何も言えなくなってしまう。
本の中で『なぜ考えを問うことはつらくなると思われるのだろうか。』という一文がある。
たしかに。
私もつらい作業だと思っていたました。
でも、この本を読んで「悩む」ということが楽しくなったのは間違いないし、誰かとともに「なんでだろうねー」と曖昧な返事をしながら深く深く潜っていくことを苦しいものだと思わなくなりました。
表面的な簡単な言葉で「わかったふり」をしたとしても、“あなた”を知ることはできない。
もっともっと深く、ともに「わからない」に潜ることで、もしかしたら「あなたと分かり合えない絶望」をほんの少しやわらげられるのかもしれない。
いや、ともに「分かり合えない絶望」を持っていることを知って、安心するのかもしれない。
「わからない」を恐れなくてよい。
とことん「悩む」。
そして、「問う」。
永井さんの言葉は、しんしんとぼたん雪が降りしきる薄暗い朝に、冷たくて重いけどやわらかい何かがじんわり広がっていくように私の胸に沁み渡る。
哲学とは「なんで?」と問うことであり、その問いは高尚である必要はないと永井さんは言う。
「なんで生きているのか」「なんで世界は存在するのか」なんて問いだけじゃなくて、「なんで社外でも同僚とLINEでつながらなきゃいけないのか」「なんでパートナーがいて幸せなのに浮気したくなるのか」とかでもいい。(p131)
なーんだ、そんな簡単なことだったんだ!と思った。
それから悩みごとや心配事があるたびに「今、私は哲学をしている」と思い出している。
すると、心がふっと軽くなって、なんだか楽しくなってくる。
どうして悩むと苦しくなるのかというと、苦しみと一体化してしまっているからだそうです。
だから、一体化してしまっている“悩み”を私から引きはがし、目の前に座らせて“悩み”の姿を見ることでそれ以上“悩み”に侵食されなくなる。
その時の魔法の呪文が「なんで?」なのです。
これは世のお母さんがよく言う「なんであんたは宿題やってないの!」という怒りを含んだ責めの言葉ではなく、「なんであなたは宿題をやる気になれないんだろうね?」という科学者的なマインドの方です。
どうして私はいつも上手くやれないんだろう。
なんでいっつもこうなるんだろう。
あいつムカつく!
を“問い”として私から引きはがしてみると、
なんで私はいつも上手くやれないと思ってしまうんだろう?
なんでいっつも同じ目に遭うんだろう?
なんであいつにムカつく!って思ってるんだろう?
悩みを“問い”として捉えた時に、私の中で大きくうねっていた感情の渦が凪になって地面の石ころをコロコロと転がすだけになっていることに気づくのです。
一番心に残った一節
ここまでも【水中の哲学者たち】を読んで変わってきた自分の内面について書いてきましたが、あえて「一番心に残った一節」を選ぶとしたら、
「どうか、変わることをおそれないでください」(p092 )
この一文である。
これは永井さんが大学の先生と哲学対話イベントに呼ばれた時に、ファシリテーターである先生が哲学対話のルール説明の最後に仰った言葉だ。
「変わることをおそれない」
私にとっては魔法の言葉だった。
私は無知な癖に頑固なので、一度決めたことを曲げるのにかなり抵抗があるタイプです。
けれど、誰かの話を聞いた時にあっさりと「それいいやん!」と思って、それまでと正反対の意見を採用したくなったりする。
でも、変に真面目な私は一貫性がないと誠実じゃない!と思ってしまって、なかなかそれまでのやり方を変えることができませんでした。
当然、気分でコロコロ意見を変えて、他人を振り回したりするのはどうかと思う。
だけど、自分の間違いを認めて「やっぱり変える」とすることは成長することに繋がるのではないか?
また、「変わる」というとそれまでの自分を否定して非を認めるような感じがするから、簡単にそれまでの自分を「捨てるなんて…」という気持ちになるのかもしれない。
そう、変わることは“捨てる”とか“間違い”“自己否定”だと思っていたんです。
だから、「変わる」ことにものすごく抵抗があった。
けれど、「変わる」ことは対立を高次に向けて引き上げていくことであり、「変容」「発展」であるということ。
これがアウフヘーベンなんだ!
なんだ、我々は哲学をきちんと学んでいなくても、アウフヘーベンできていたじゃないか!
それからというもの、私は「変わる」ことを恐れなくなった。
自分の意見を変えたり、やり方を変えたり、態度を変えたり…いろんな「変わる」があるけれど、「変わる」というのは前に進むためのステップの1つであるということを素直に認められるようになったんです。
大勢の人と関わるからこそ変わらない一本の芯を持っていないといけないと思っていたけれど、「変わってもよい」という柔軟性を持ってみると、とても楽しい。
誰かの考えを聞いて「それいいやん!」と思った時に、「変わってもよい」を自分の中に持っていると、それまで自分が信じていたものがすべて0になってしまうのではなく、それまでのものが砂のお城のようにサラサラと崩れていった後に、お城を構成していた砂と別の新しい白い砂と交じり合って、まったく違う形のお城を建て直すような感じ。
「変わってもいい」
私の中の呪いをまた1つ解いてもらった言葉です。
それまでは、たとえばあるところに就職してから初日で「あ、合わないかも」と思っても、我慢して5年働いたりしていた。
ある集団に所属した時に違和感を感じて、その違和感が大きくなっていっても抜け出せなかったりしていた。
一度読み始めた本は読み終わるまで他の本は読めない!と思っていたので、読みづらい本を3か月とかそれ以上かけてちびちび読んでいたりした。
それを「変えてもいい」と思ってみると、なんだか難しく考えていたことがいとも簡単にほどけるような気がしてくるから不思議だ。
ある時に、永井さんご本人とお話する機会があったので、思い切って聞いてみたことがあります。
「会話をしていて、アドバイスしたくなったりすることはありませんか?」と。
私は人にアドバイスをされるのが嫌いな癖に、人にはアドバイスしたくなってしまう。
普段の会話で自分がアドバイスをされることの多さもあって、“対話”を各地でされている永井さんはどうなのだろうとずっと気になっていました。
永井さんは「うーん、ないかな」と仰った。
それは、『哲学対話』という場だからと教えてくださった。
【水中の哲学者たち】の中でも、“哲学対話は闘技場ではあり得ない”と書かれている。
といっても、共感の共同体でもない。
ディアレクティケー、つまり「弁証法」なのだ。
そう思った時に、それまで頑なに「変えてはいけない!」と思い込んで一貫性を持つことに徹しながら苦しんでいた私は、何かと戦っていたのかもしれないとハッと気づいた。
先ほど上で「なんで?と問うことは哲学の始まり」と書いていましたが、「悩んでもがく」ことと「変わらないを貫いて苦しくなる」ことはなんだか同じなような気がしてきました。
悩みに対して「なんで?」と問うことも、「変わる」ことの手段の1つなのだと思います。
悩んでもがいてる時って「こうあらねば!」「あの人は絶対にこうだ!」とか思い込んで、視野が狭くなっていますよね。
だから「なんで?」と問い直した時に、違う視点で見えてくるものがある。
それは「変わる」の一歩なんだと思います。
悩みに対して「なんで?」と問いたくない時――大嶋メソッドでいうと心に聞けない時――それはもしかしたら、変わることをいけないことだと思っている時なのかもしれません。
読後に湧いた感情・気づき・小さな変化
私は毎朝起きたらすぐに読書を始めるのですが、【水中の哲学者たち】を読んでいる時は朝になってページを開けるのがすごくうれしかった。
私は学生時代から人間関係を上手に築くことができなくて、1人で過ごすことの方が多かったのですが、この本を読んでいる間は誰にも言えない寂しい孤独感をなにかやわらかいもので撫でてほぐしてもらっているような感じがしていました。
そして、「ああ、もしかしたら寂しいのは私だけではないのかもしれない」と気づかされる。
世界は“さびしい”で溢れているのかもしれないけれど、みんなが持っている“さびしい”に気づいた時に、「私も」と壁を取っ払えるような気がしたんです。
だから、「私だけかもしれない」という孤独感を電車で隣に座ったきれいなお姉さんも感じているのかもしれないし、道端でぶつかってくるおじさんも孤独感に溺れそうになっているのかもしれない。
それを「キー!ムカつく!」と感情に飲まれるのは簡単だし、今まで散々やってきたので、「なんで?」と問い直してみると、そこからいろんな可能性が生まれてくる。
すると今まで感じたことがなかった「考えるのって、こんなに楽しかったんだ!」という感覚が湧いてきました。
大学で心理学を勉強していた頃、「考えること」はとても辛い作業でした。
あの人の気持ちが分からない、数年後にこの苦しさがなくなっているのかが分からない、このままでいいのか分からない…だけど、どれも目に見えないものばかりで、考えても考えても答が出なかった。
その答を少しでも知りたいと思って心理学を学んだんだけれど、教科書には明確な答は書いてなかったんです。
永井さんは、“昔読んだわけのわからない哲学書は、世界のわけのわからなさをそのおまま伝えるしかなかったんじゃないか”と仰っている。
そうか、世界が「わからなくてこわい」と思っていたのは、私だけじゃなかったのかと安堵した。
みんなこのわけのわからない世界で、なんとか「正解らしきもの」を見つけようとして「なんで?」に潜って考えたりしているんだ。
この本を読んで、私の中の「こわい」がやわらぎました。
わけのわからないものなんだ、わけがわからないって思っていいんだ!って。
「飛ぶ」に書かれているのですが、永井さんも人前で話すことがこわかったそうです。
「え!本を出版しているような立派な人でも、人がこわかった過去があるのか!」と驚きました。
そりゃそうだろ、と思う方もいらっしゃると思いますが、【水中の哲学者たち】の中の言葉たちは永井さんのユーモラスな面が見え、美しくやさしいイメージなので、まさか「話すのがこわい」という感覚を持っている人のようには思えないんです。
だけど、“他者を傷つけないか、おそれながら話すこと。他者に傷つけられないか、おそれながら聞くこと。”この一文を読んだ時に「そうそうそうそう!」と激しく同意しました。
私も人と話すのがずっとこわかった。
それは、自分の言葉で相手が怒ったり悲しんだりするのがこわかったからだし、相手の何気ない言葉に不用意に傷つきたくなかったから。
それでいつもへらへらした返答をしていたら、逆に怒られたりする。
でも、自分の意見を言うと誰かを傷つけるんじゃないかと思うと、素直な気持ちを言えませんでした。
もしかしたら、この世に「答」なんてないかもしれない。
だって、哲学で「なんで?」と問いに足を突っ込んだ時に、それまで当たり前だと思っていた景色がどんどんその姿を変えていくから。
永井さんは“哲学はわたしたちの目を見えるようにするどころか、より見えなくする”と仰っている。
それでも、哲学対話のように誰かと一緒に問うて考えるのが「楽しい!」と感じるのは、私の世界が広がるからだと思っています。
それは「変わること」の楽しさであり、他者の考えを否定せずに聞いた時に「なるほど」と思ってそれまでの枠組みがなくなって新しい世界の風が吹く。
永井さんは考えごとをしている時に、「パキパキパキパキ」「ガシャン」「おわあああああん」といろんな音が聞こえてくると書いていて、誰かの話を聞いた時に「ガーン!」という衝撃がくるとも仰っていた。
わかる。
私の場合はそこに突風が吹いたり、眩い光が射したり、心の中の視界が開けたりもする。
私もたくさんの人のお話を聞く仕事をしていますが、聞けば聞くほど「わからなくなる」ので、たとえば自分の意見を求められたりすると「なんででしょうねえ」とはぐらかしてしまったりする。
相手は私に何かを期待して聞いてくださったのかもしれないし、そうじゃないかもしれない。
けれど、私は無責任に「なんででしょうねえ」と適当に答えてしまう。
その「なんででしょうねえ」の中には、〇〇という答や△△という答や□□という答が瞬時に脳内にバババッと出てきたけれど、結局どれも真理じゃないような気がしてしまって、でもすべてを含んだ意味合いで言っていたりする。
「わからない」んですよ。
だから、問うことを恐れなくなりました。
今までは人に問うことは恥だと思っていたし、「あなたのことを理解しているよ」という意味を伝えるためにわかっていることを一生懸命に伝えようとしてきました。
だけど「わかるよ」と共感するよりも、「あなたはどう思っているの?」と問うことの方が、あなたをもっと深く知れると知ったんです。
そして、問うことで深くあなたに共感できるような気がするんです。
この本がそっと寄り添う相手はどんな人か
人がこわい、信じれる人が誰もいない、誰とも仲良くなれない…そんな思いをひっそりと抱えている人の心をあたたく照らしてくれる本です。
大嶋先生の【誰もわかってくれない「孤独」がすぐ消える本】に「自分の孤独の色で相手を照らした時に、相手の孤独に自分も照らされて凪になる」ということが書かれていましたが、【水中の哲学者たち】はまさに永井さんの中にあった孤独で照らされてやさしく輝けるような感じ。
今日あった嫌なことも、ムカつくあいつも、気分が落ち込むようなことも、読めばじんわりと身体に沁み渡ってふつふつと自分のエネルギーに変えてくれます。
そして、世界に感じていた違和感を言葉にしてくださっているので、もがくのをやめて「これでいいんだ」と納得させてくれるようです。
わかりあえないと悲しんでいたし、誰にも本当の自分は理解してもらえないと絶望していた。
けれど、「わかり合えないから問う」ということを教えてもらいました。
まとめ
他にもたくさんの名言があります!
「もう少しでわかりそう」という感覚は、「もう少しで思い出せそう」という感覚に似ている。(p20)
わかる。
「あーあれなんだっけなあ!」と「もうちょっとで何か掴めるのになあ」っていう感覚。
どちらも記憶の底にあるんだけれど、もう少し深く手を伸ばさないと届かないもどかしさ。
対話をするとは、他者に出会うことだなあと思う。(p231)
通勤電車とか隣の家の人とか、毎日顔を合わす人はいる。
でも、対話をしてはじめて「そうだったんだ!」とその人のことを知った時の感動がきっと「あなたと出会えた」という実感に繋がるのかもしれない。
ただ顔を知っていることと、その人の考えや内面を知ることは違うことなんだなあ。
しかし、子供にとって「なんで?」というのは、しばしば怒られているときに聞く言葉でもある。(p245)
「なんで?」と自分自身や他人に問うことに抵抗があったのは、この感覚があったからかもしれません。
否定ではなく「あなたを知りたいの!」という意味での「なんで?」は、私の心も相手の世界も豊かにしてくれるような気がします。
他者を愛しながら他者をめんどくさがるわたしも、それなりに味があるだろうか。(p251)
ほんっとうによくわかる!
これは永井さんが電話で友人の話を聞きながらレジュメを作っていたエピソードに出てくるのですが、どうして大切なのに、愛したいのに、無責任に自分勝手に振る舞ってしまうんだろう?
人が好きなのに矛盾した行動を取ってしまうのは、決して人間ができていないわけではなく“多面体”なのだ。
美しくなくていい、一貫してなくていい、私もあなたもズルいところがあって不誠実なところもある。
人間ってだから愛しくなるんだよね、きっと。
👇以前に書いた【水中の哲学者たち】を読んだ後の記事です
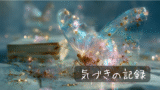
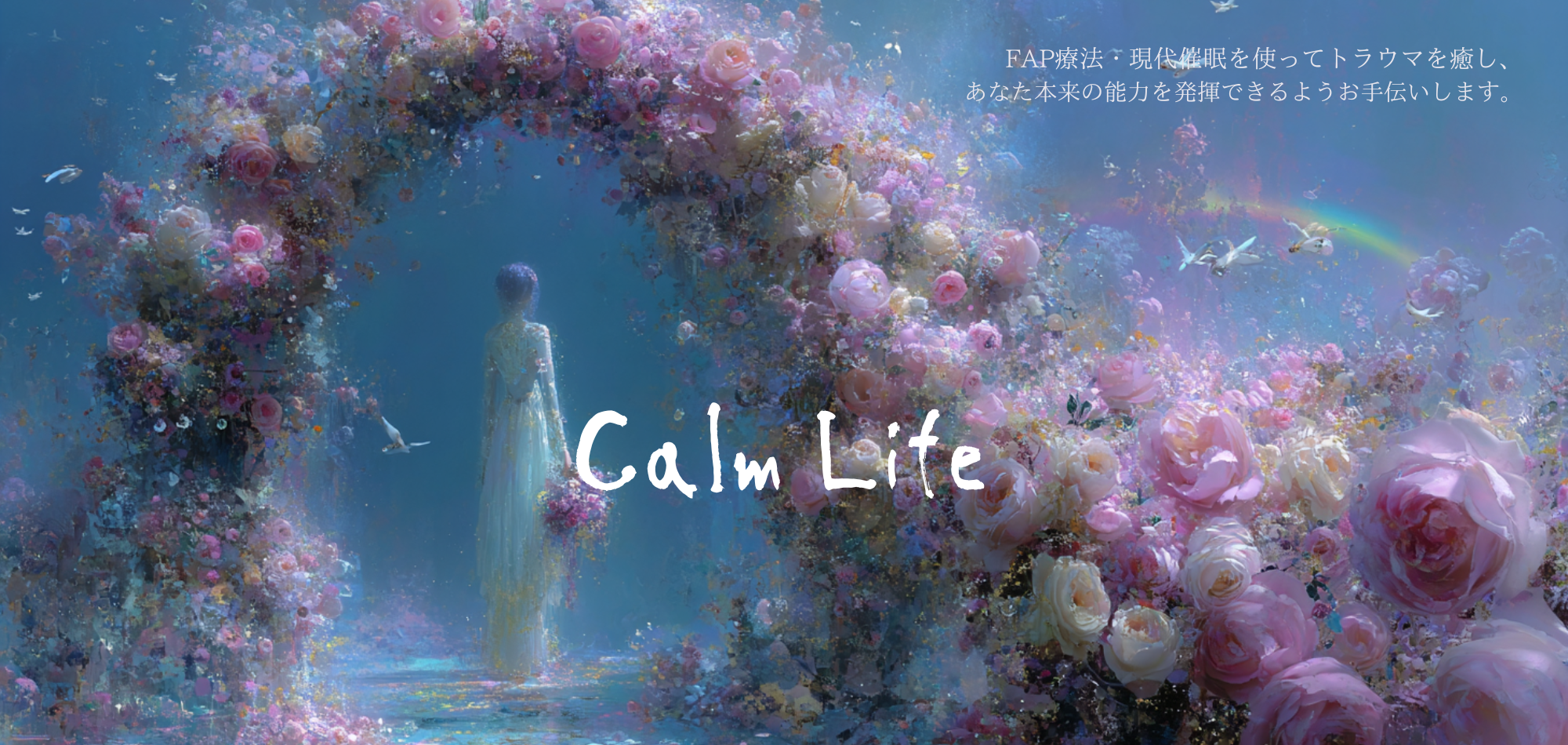






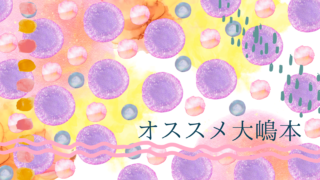



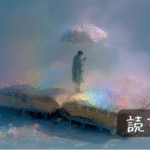

コメント