大嶋先生のブログにちょこちょこ出てくるヴィクトール・E・フランクル博士の【夜と霧】。
ずっと読まねば読まねばと思いつつ数年経っていて、その間に【死と愛】を先に読めと中指ビンゴに言われて読んだら難し過ぎて挫折して、さらに年月が経った今。
読むのを避けてきた理由の1つに、「読んだら落ち込むんじゃないか」という不安がありました。
でも、読み終わった今は、もっと早く読めば良かったと思っています。
そんな【夜と霧】のレビューを今回は紹介させていただきます。
どんな本?
私が今回読んだのは2002年11月に発売されたみすず書房の新版です。
池田香代子さん訳のものです。
旧版もまだ絶版になっておらず、書店に売っていると思います。
旧版は霜山徳爾さん訳です。
初版は1956年に出て、その後1977年に一部表現を変えた改訂版が出版されています。
これは訳者あとがきで解説されています。
内容は、心理学者のヴィクトール・フランクル博士が体験した、ナチス・ドイツの強制収容所の話です。
収容所収監から解放後までの出来事が時系列で書かれており、それを見て体験したからこそ見えてきた「生きること」についてが記されています。
収容所に突然連れてこられた時の選別の様子、極寒の中ぼろぼろの靴とは言えない靴で労働をさせられる様子、意味もなく体罰をされること、ひどい空腹感の凌ぎ方、蔓延する病気など、未来など全く見えない中での人間の精神状態の推移が書かれています。
『夜と霧』というのは、ナチス自身がつけた「占領地の反ドイツと目された政治家や活動家を連行せよ」という命令の通称です。
つまり、夜陰に乗じて人々を連れ去り、霧のように消してしまうという意味だそうです。
先に読んだ先輩に教えていただいのですが、旧版は戦争の悲惨な写真がたくさん掲載されているそうです。
私が持っている新版には、写真は1枚も載っていません。
読もうと思ったキッカケ
数年前に、中指ビンゴに先に【死と愛】を読めと言われて素直に読んでいました。
確かにロゴセラピーを学ぼうと思ったら、直接【死と愛】を読んだ方が早いんじゃないかと思ってました。
でも、きちんと心理学を学んで、精神分析やフロイトのこと、哲学なども理解していないと、かなり難しい内容でした。
ゆえに、大学時代で心理学の勉強が止まっていた私は、20数頁で挫折してしまったんです…。
しかし、【死と愛】を挫折した後も、なかなか【夜と霧】を読もうとはなりませんでした。
なぜなら、心を痛めるような悲惨な体験がつらつらと書かれているんじゃないかと思っていたからです。
何の罪もない人々がある日突然、強制収容所に連行されて死を迎えるだなんて…想像するだけで恐ろしい。
自分の身にそんなことが起ころうものなら発狂してしまいそうですし、自分じゃない誰かがそんな目に遭った話を聞くのは、どこに怒りを向けていいのか分からない。
そんなことを考えながら、積読したまま5年以上は経ったと思います。
けれど、ある時、すでに【夜と霧】を先に読んだ先輩に「読みやすい」と教えてもらいました。
小説のような感じで読めると聞いたので、本棚に眠っていたこの本をついに手に取ったのです。
心に響いた3選
教えていただいた通り、本当に読みやすかったです。
私がきっと恐れていたこと、それは恐らく痛ましい描写や残酷な描写があるかもしれないということが気になっていたのでしょう。
たしかに人間を人間と思わないような扱いをされた体験が書かれていますが、けれどフランクル博士はいたずらに残酷な描写をして、自分がどれだけ悲惨な体験をしたかを世間に伝えたかったわけではないはずです。
強制収容所で命を落とした方はたくさんいます。
しかし、その中でフランクル博士は最後まで生き延びて、そして自身の心理療法を確立されました。
【夜と霧】を読むだけでも十分、フランクル博士の考える「生きる」ということについて学べます。
苦しむことの意味
苦しむことはなにかをなしとげること(p132)
私は、平和な日本に生まれ、生きてきました。
強制収容所での生活は常に死と隣合わせです。
だけど、戦争も経験したことがない私でも、強制収容所の人々と同じように生死の危機や絶望を感じていました。
未来に希望が持てず、来る日も来る日も過酷な日々。
いっそもうすべてを諦めてしまった方が楽なんじゃないかと思うような苦しさの中、それでも収容所で生き延びて来られた方の痛みは私の想像の何百倍だろうと思います。
苦しい、苦しい、逃げたい、と思えば思うほど自我を失ってパニックになっていくような気がします。
しかし、フランクルは「苦しむことですら課題だった」と言います。
苦しみや絶望なんて感じたくない、そんなものなければいいのにと、何度人生で憎らしく思ってきたことか。
だけど、フランクルはリルケの言葉を引用して「苦しみ尽くす」と言っています。
それは、大嶋信頼先生の言うところの「焼豚を作る」を思い出します。
苦しみは、なければないほど良いものだと思っていました。
苦しみは人生から排除すべきもので、その苦しみがあるからいつまで経っても自分の人生はよくならないんだと。
でも、フランクルは言います。
だが、涙を恥じることはない。この涙は、苦しむ勇気をもっていることの証だからだ。(p132)
私はこの一文を読んだ時に、自分は何らかしらの人生の問題にぶち当たって苦しんでいる自分を恥じているのだと気づいたんです。
他の人のように生きれない不器用な人間だから、こんな不幸な目に遭うのだと。
そうではなくて、私が今悩み苦しんでいるのは、「勇気を持っている」ことの証なんだと知った時、恥じる気持ちが消えて、苦しみ悩む自分を誇りに思えました。
苦しんで流す涙はドロドロの醜い薄汚れたものだと思っていたのですが、実は苦しみこそが美しく気高くあろうとする私の人間の心だったのかもしれません。
人間が人間らしく生きるとは?
「生きる意味」というのは、人生が私にもたらしてくれるものだと思っていました。
だから、たとえばいい子でいれば幸せになれるはずだとか、人に親切にしていれば苦労しないとか、そんなことを人生に期待していました。
しかし、収容所の日々、いや現代に生きる我々であっても、生きるか死ぬかの決断の連続なのではないだろうか。
ただ、我々の目の前にはすぐに死の脅威が現れないだけであって、内心の決断を下す瞬間というものは何度も訪れる。
収容所では、ある選択でガス室行きになったり、それを逃れたり、まさに運命に翻弄されるようである。
何もしていないのに、監視兵に突然殴られたりする。
これを戦争のない現代に置き換えて考えると、理不尽に上司に怒鳴られたり、道端ですれ違った人に因縁をつけられたりということかもしれない。
今まさに死の縁にいる人からしたら「そんなもんとは全く恐怖が違う!」と思うかもしれませんが、トラウマ持ちの我々にとったら、死に匹敵する恐怖です。
そんな時に、「もう怒られたくない…」「こんな生活は嫌だ…」と心が折れてしまう人と折れない人の差は何か?
先に【死と愛】を半分読んでいた私は、その答をなんとなく知っていました。
それは、「能動的に生きる」ということです。
だけど、実際に自殺未遂を何度もしたことがある私は、「そんなことは分かっていても、できないでしょ!」と思っていた。
「能動的に生きる」ことの納得する答が欲しかった私は、【夜と霧】を読んで「生きるとは何か」が腑に落ちました。
人間として破綻した収容所生活の中であまりに辛い体験で感情を消失し、生きる意味を見失っていく人がいる中で、「わたし」を見失わなかった人たちがごく少数存在します。
フランクル博士は、「内的なよりどころ」を持つことが人間らしく生きることであると言います。
つまり、内的なよりどころがない脆弱な者は、あまりの辛さに精神崩壊をしてしまう。
それは、節操を失い、人間としての尊厳を自ら墜落させてしまうようなことです。
どんなに辛い状況であっても、人間が人間らしく生きるためには「内的なよりどころ」すなわち「生きる目的」が必要です。
今、「もう生きていたくない。目的なんかない」と思っている方もいると思います。
私もそうだったからです。
だけど、外面的に破綻し、死をも避けられない状況の収容所において、「未来の目的」を持ったことで生き延びた人がいます。
それは、「生きてもう一度家族に会いたい」だったり、「解放されたら論文を発表しよう」だったり、そんなことで良いのです。
未来に目を向けて、「よりどころ」を思い出すだけで良いのです。
死に至る自己放棄とは、未来の喪失から起こるからです。
わたしたちが生きることからなにかを期待するかではなく、むしろひたすら、生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題なのだ、ということを学び、絶望している人間に伝えねばならない。(p129)
私は、人生が生きる意味を与えてくれるものだと思っていた。
だから、「なんで自分ばっかりこんな目に遭うんだ!」と憤っていたし、みんなが幸せに見えていたから自分が惨めで仕方なかった。
でも、我々は死のその瞬間まで「どのように生きるか」を自ら選択することができるのだ。
「なぜ生きるかを知っている者は、どのように生きることにも耐える」(p128)
生きる目的を失うとたちまち崩れてしまいます。
けれど、生きる目的をことあるごとに意識し、「どのように生きるか」を思い出すことで、たとえ不遇な状況にあろうとも、自分を見失うことなく誇りをもって苦しむのです。
そうすることで、自らの人生に意味を見出せるのではないでしょうか。
生き延びた「英雄」
フランクル博士は収容所から解放された第三段階として、精神的な抑圧から突然に解放された人間をゆがめるおそれのある深刻な体験を3つ、述べられています。
1つ目は、長く権力や暴力にさらされた未成熟な人間は、「今度は自分が力と自由を思うままに、とことんためらいなく使っていいんだ!」と履き違えてしまうこと。
理不尽な状況に長く置かれる間に、「自分も他人に対して非常識であっていい!」と思い込んでしまっているような状態です。
2つ目は、不満。
自由を得て元の暮らしに戻った時に、世間から「こっちも大変だったんだよ」「あなたに何が起こっていたのか、何も知らなかったので…」という人々の声を聞いた時。
長く耐えてきたその人の不満は膨れ上がります。
決して賞讃されたかったわけではない。
けれど、自分は何のためにあのすべてを耐え忍んだのだ、と悩まされる。
そして、3つ目の失意。
フランクル博士は、先に【(強制収容所の)人間を精神的にしっかりさせるためには、未来の目的を見つめさせること】であり、それはつまり、【誰かが自分を待ってくれている、人生が自分を待っているのだ、ということを常に思い出させることが重要だった】と述べています。
しかし、収容所で唯一心の支えにしていた家族が、解放後にもういなかったら…?
死と隣合わせの状況で何度も何度も思い出して夢に描いていたあの瞬間が、思い描いていたものとは違うことが分かった時…。
それまで「よりどころ」にしていたものがなくなり、生きる支えを失ってしまいます。
これは、心に傷を持っている我々にも同じことが言えるのではないでしょうか。
幼少期に、長期にわたってトラウマ体験をすると、他人に対して支配的になってしまったり、心を許した人物に行き過ぎた暴言を吐いてしまったりします。
自分は相手を傷つけるつもりはなく、「今まで不当な扱いをされてきたんだから!」と自分の権利を主張するようにやっていまします。
そして、「自分は大変だったんだ」と何度も何度も訴えるのだけれど、他人からは「私もそんな経験あるよ」と言われたりして、「自分の苦労は大したことないのかもしれない…」と勝手に落ち込みます。
さらに、「ここを出れば自由になれる!」と思って出た先に、思い描いていた自由と違ってなかなか社会に受け入れられない状況が続いたとしたら…?
もしかしたら、私たちも収容所にいるのかもしれない。
目の前で死を目の当たりにしていなくても、心を抑圧され、権力や暴力で支配されている。
だからこそ、もしある時、急にその抑圧された状況から解放されたら、誰に賞讃されなくても「よく耐え忍んできた!」と自分で自分を褒めてみる。
別に褒められたくて耐え忍んでたわけではないけれど、自分はその苦しみを耐え抜いた「英雄」だと自分自身で認めてみてもいいのではないだろうか。
『夜と霧』を読んで変化した自分
長年、「死にたい」と言っている人に何と言えばいいのだろう?と考えてきました。
なぜなら、自分が「もう生きていたくない」と思っていた時に、誰に苦しみを打ち明けても絶望は拭えなかったから。
だけど、生きるとは、自らが人生に意味を見出すことであると知った時、フランクル博士の言う「能動的に生きること」がやっと理解できたんです。
正直、【死と愛】を読んだ時点では、「生きる希望を見つけるって言ったって、それが分かればやってるよ!」と思っていました。
(最後まで読んだら腑に落ちていたのかもしれませんが…)
「死にたい」と思っている時にそんなことを繰り返し言われたって、「いい加減にして!」と思ってしまう、と。
しかし、そのように考えてしまうのは、人生に対して受動的だったからです。
生きているだけで、人生は棚ぼたのように幸福をくれると思っていたのかもしれません。
そうでなくても、「努力すれば報われる」とか何かしらのご褒美を期待していたと思います。
「こんなに私には頑張っているのに!」と。
フランクル博士は言います。
多くの収容所の人々の心を悩ませていたのは、収容所を生き抜くことができるのかということだったと。
生き延びれないなら、今の苦しみには意味がない。
しかし、フランクル博士は逆のことを考えていました。
【わたしたちを取り巻くこのすべての苦しみや死には意味があるのか】と。
もし、自分は運命に翻弄されるだけで、自分の力では何もコントロールできない、自分のことさえも自分に主導権がないと思い込んでしまったら、自分の人生を放棄してしまいたくなりますよね。
フランクル博士はさらに言います。
それは何も強制収容所に限ることではなく、人間はどこにいても運命と対峙させられて、ただただ苦しいという状況から何かを成し遂げるかどうかという決断を迫られるということを。
苦しみの前に、ただの無力な人間として無抵抗のままでひれ伏すのか、それとも、この苦しみを好機だと思って、生きる視点を変えてみるのか。
人間の強さとは、そこにあるようなのです。
収容所の中で亡くなった若い女性の物語があります。
その女性は、もうあと数日で自分が死ぬことを悟っていました。
しかし、「運命に感謝しています。だって、わたしをこんなにひどい目にあわせてくれたんですもの」と晴れやかな気持ちで言うのです。
この時の女性の気持ちを想像できるでしょうか。
女性は、以前は何不自由なく甘やかされて暮らしていて、その時には精神がどうこうなんて真剣に考えたことがなかったそうです。
決して苦しんだ体験や、今苦しんでいる体験を美談として語りたいのではありません。
しかし、苦しんだからこそ精神的に人間として、目覚ましく成長することができるのです。
苦悩があったからこそ、高みに到達することができるのです。
私は、この本を読んでから苦しいことにぶち当たった時に、「苦しみは私を成長させてくれる」と思い出しています。
ただただ耐え忍ぶだけではないのです。
そして、苦しんでいる時に自己放棄をするのではなく、「苦しい中だからこそ、私はよりどうありたいかが問われている」と思っています。
少し脱線しますが、私の好きな漫画の1つに【左ききのエレン】があります。
その中で「クソみたいな日にいいもんつくるのがプロだ」って台詞があるのですが、私はこの言葉が大好きなんです。
体調が良い日は良いものを作れるのが当たり前じゃないですか。
だからこそ、不安定な時にどれだけのものを作れるかが問われる。
想定外のトラブルがあった時に、その人の本性が見えるじゃないですが、そんなことを思い出しました。
私が憧れるのは、強く気高い心を持って生きる人です。
脆弱で、人に遜って、自分の運命を他人に委ねるような生き方をしたいのではない、とこの本を読んではっきりと自覚させられました。
中には「人間的に成長したいわけじゃない!この苦しみをなくしたいだけ!」と思う方もいると思います。
私が以前はそう思っていたので言いますが、もしかしたら「苦しい」のは人間としての誇りか生きる目的か心のよりどころがないからなのかもしれません。
苦しみをやわらげる薬は、この3つなのかもしれません。
まとめ
もし今、毎日が苦しい、逃げられないと思っている人がいるなら、試しに読んでみてほしいと思っています。
逃れられない運命に屈服して精神崩壊することは一瞬でできます。
ただ、私は精神崩壊をするよりも、人間らしくプライドをもって毅然と向き合う方が、はるかに苦しくないのではないかと今では思っています。
たしかに、逃げることも覚悟して向き合うことも、どちらにも苦しみは伴います。
しかし、自分の尊厳を守って生きることを選ぶほうが、心の痛みは少ないと感じています。
苦しんだ分だけ、私は何かを成し遂げようとしています。
苦しんだ分だけ、私は人間的に高みに近づいていきます。
苦しむことは、強いからできるんです。
そんなことを、【夜と霧】から教えてもらいました。
人生を変える一冊です。
大嶋信頼先生の理論を深く理解する手助けにもなると思います。
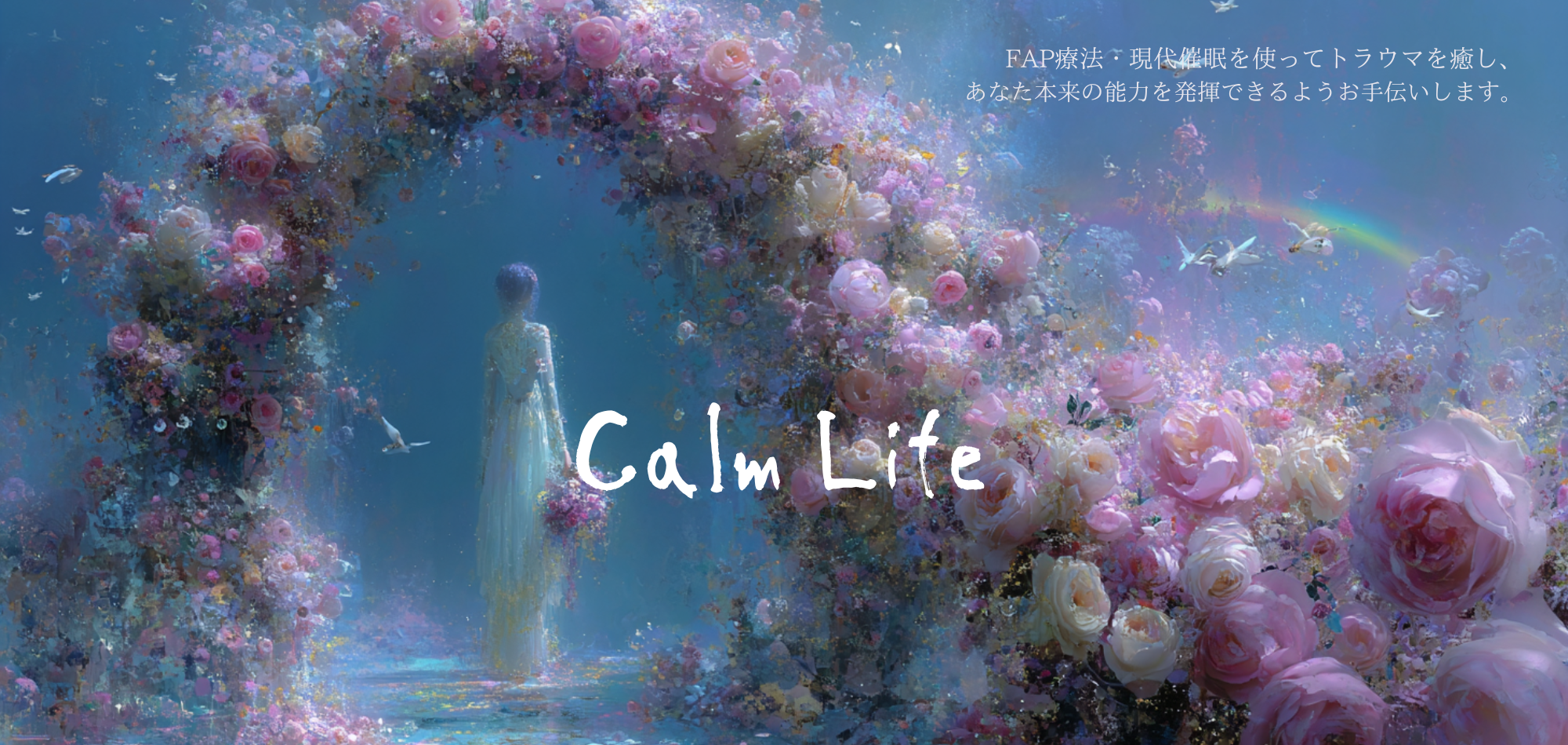

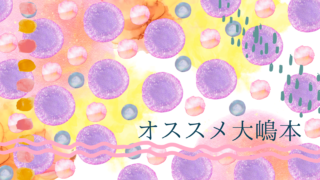









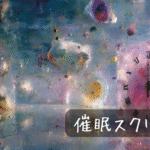
コメント